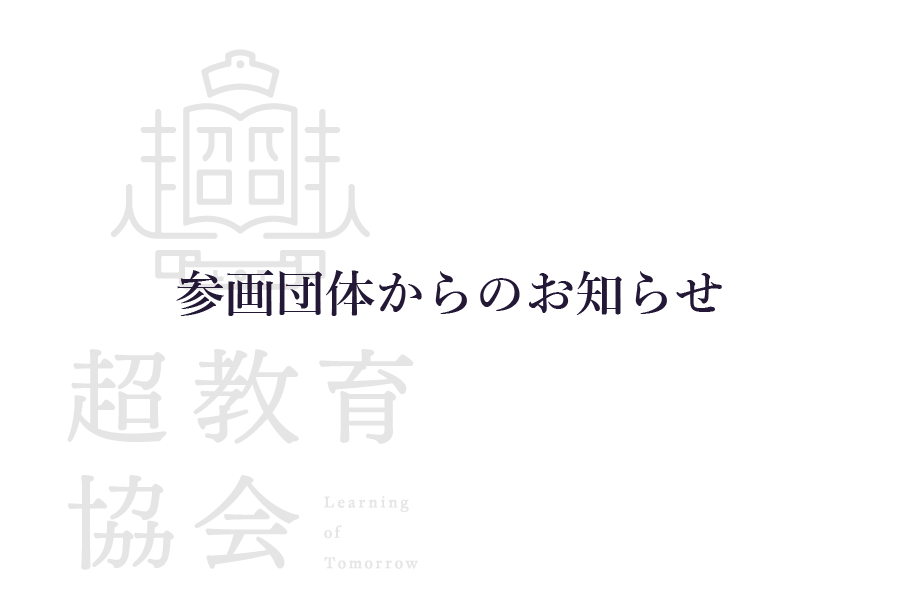概要
超教育協会は、2021年11月10日、株式会社e-Craft 代表取締役CEOの額田 一利氏を招いて、「デザイン思考を用いたCtoCプラットフォーム教育〜embotによるプロトタイピング体験〜 」と題したオンラインシンポジウムを開催した。
シンポジウムの前半は、額田氏がプログラミング教材「embot」開発の背景などを紹介。後半には、超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに視聴者を交えての質疑応答を実施した。その模様を紹介する。
>> 前半のレポートはこちら
>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画
「デザイン思考を用いたCtoCプラットフォーム教育
〜embotによるプロトタイピング体験〜」
■日時:2021年11月10日(水)12時~12時55分
■講演:額田一利氏
株式会社e-Craft 代表取締役CEO
■ファシリテーター:石戸奈々子
超教育協会理事長

▲ 写真・ファシリテーターを務めた
超教育協会理事長の石戸 奈々子
額田氏は約30分の講演において、代表を務める 株式会社e-Craftが提供しているプログラミング教材embotの開発背景や、子どもたちのためのデザイン思考を用いたCtoCプラットフォームについて解説した。おもな講演内容は以下のとおり。
シンポジウムの後半では、超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、参加者からの質問に額田氏が答えるかたりで質疑応答が行われた。
子どもたちが自主的にプログラミング教育に興味を持つ そんな場をつくるのが重要
石戸:「まずは、デザイン思考など考え方を学ぶことを含めたカリキュラムは具体的にどういうものなのかということと、CtoCプラットフォームのもう少し具体的なイメージ、この2点についてお話ください」
額田氏:「デザイン思考は、一時期、企業で盛んに言われていましたが、子ども向けに勉強するような内容ではなく、高尚な言葉で表現されていました。デザイン思考をインターネットで検索すると分かりますが、抽象的で概念的な話が多いのです。今回、子どもたちに体験してもらおうと考えていたのが、なるべくゲーム感覚で自然にデザインや、人を喜ばせることを考えてもらおうということです。
最初は連想ゲームみたいなところからスタートするカリキュラムになっています。例えば、誕生日プレゼントに何をあげますかと質問すると、誰にあげるのか分からないので答えも曖昧になりますが、『母の日に何をあげますか』と質問すると考えが揃ってきます。自然に生活のなかで人を喜ばせるとか人に対して何かしてあげるのは、子どもでも経験しているので、そういう経験を掘り起こしていくのがカリキュラムの中には入っています。お父さん・お母さんを喜ばせて、お父さん・お母さんから返ってきたフィードバックを分析するのもカリキュラムに入っていて、なぜこのような評価が返ってきたのか子どもたちと一緒に考えます。
CtoCプラットフォームでは、できれば販売をする経験をしてほしい。自分もメルカリなどに服などを出品していますが、すぐ売れるものと全然売れないものがあります。子どもたちにも、なんで売れないのだろうと考え、ユーザーに対して販売品のよいところを伝えることを、CtoCプラットフォームのなかで経験してほしい。平たく言うとメルカリのプログラミング教育版がやりたいのがCtoCプラットフォームなので、イメージ的にはみんなが投稿してきたものを自分で値段をつけて、子どもたちが仮想通貨で買う。そういうのをCtoCプラットフォームで実現したいです」
石戸:「視聴者からも『カリキュラムには具体的にどのようなものがあるのか、いくつか教えてください』という質問がきています。まず、学校の中ではどのような教科でどのような授業がされているのか。もうひとつは学校外だとどういったカリキュラムなのかについて教えてください」
額田氏:「学校の中では、embotを教材として多種多様に使ってもらっています。プログラミング教育の専門的な話になりますが、プログラミング教育はABCDEFに分類されていて、Aの領域は算数や理科と教科が決まっていて授業の中でやるもの。DやEの領域はクラブ活動や教育課程外のものになります。授業の中で扱うものは『やること』が、がちっと決まっていて、多角形をembotで描いたり、理科では回路を使うなど、教科書とリンクしているような内容になっています。
算数や理科以外では、総合的な学習の時間で地域を盛り上げるためにはどうすればよいんだろうなど考える取り組みをしています。総合的な学習の時間で、地域を紹介するembotや、スタンプラリーをするembotをつくっている学校の先生もいます。embotを活用するニーズからくる授業のカリキュラムをつくってくれている先生もいます。総合的な学習の時間や、クラブ活動の中でも、考える力、ニーズを取り扱うことが多いのが今のembotの状況です」
石戸:「embotを選ぶ学校は、他の教材と比較してembotのどういうところに惹かれているとお考えですか」
額田氏:「ソフトウェアだけで完結していると子どもたちが関心を持ちづらいので、フィジカルなものであるということ。次に価格。embotは今6,000円で販売していますが、学校教育の現場には導入しやすい価格です。これが5万円になると、クラスに1個しか導入できませんが、安価だと多くの子どもに行き渡らせることができます。あとはキャラクターがついていること。基板むき出しの教材もありますが、そういうのに抵抗がある人もいるので、それに比べるとエントリーモデルには向いているでしょう。embotは女の子のユーザーも半分くらいいるのですが、キャラクターの力が大きいと思います。ハードウェアの観点と、価格の観点とエントリーモデルの観点。この3つだと思います」
石戸:「教育教材だけでなく玩具も含めて市場が盛り上がっていますが、当初は海外から入ってくるものが大多数でした。embotは今、玩具メーカーと組んで市販していますが、開発にあたって留意した点を教えて下さい。意識した玩具、ターゲット、狙ったポジションなどを教えてください」
額田氏:「参考にしたのはサッカーとバスケットボールです。学校の授業でもやり、お昼休みや学校が終わっても習い事としてやっている。スポーツは偉大で素敵だと思っていました。それはエンターテイメント性だと思います。スポーツにおけるエンターテイメント性は大事だと思い、サッカーやバスケットボールなどが、プログラミング教育ならできるのではないかというところに行き着いて、玩具メーカーのタカラトミーさんに話をして、一緒にやろうとなりました。
一時期は、教材メーカーなど固いメーカーとやろうと考えていたこともありましたが、エンターテイメントのところに魅力を感じました。我々は教育とエンターテイメントを合わせてエデュテイメント領域と言っていますが、その領域をターゲットにしました。NTTドコモの時も、公教育かコンシューマーかどちらをやるのかと言われましたが、それをどちらもやることに意味がある。サッカーとバスケットボールから発想を得て、ブランドもターゲットユーザーもそこからイメージしています」
石戸:「タカラトミーさんと組むことによって、新たに得た視点があれば教えてください」
額田氏:「embotで苦労したことのひとつは、Safety Toy基準に合格してSTマークを取得することでした。尖ってないかとか、口に入れて有害なものが入っていないかなど、子どもたちの安心安全に配慮することが必須でした。これは、一緒にタッグを組んでものづくりを経験しないとなかなか学び取れなかったことです。また、小さいピンみたいなのを差しますが、ピンが縦長だと手でつかみにくいが、横長だと手でつかみやすという議論までします。embotはいかにプログラミングのハードルを下げるかがひとつの課題だったので、ハードルを下げる、安心安全という観点、ユーザービリティの向上など、基礎的な部分で大変勉強になりました」
石戸:「最後に2つお伺いします。1点目は、日本でプログラミング教育の必修化が始まって半年以上が経とうとしていますが、現状についてどう思っていますか。現時点での課題と、学校現場にしたいアドバイスを知りたいです。もう1点は、会社の今後の展望についてです」
額田氏:「プログラミング教育には、色々な人が色々な立場から期待をしています。そういう思惑も大事にしていきたいですが、もう少し子どもたちのための子どもたちによる、プログラミング教育を充実させていきたいと考えています。それがCtoCプラットフォームを構築したいというところにもつながります。子どもからすると、どういうプログラミング教育がよいのか、どういうプログラミング教育が嫌なのか、大人側からの思惑や視点という観点ではない部分を盛り上げることによって、プログラミング教育はより発展していくと思います。いかに子どもたちが自主的にプログラミング教育に興味を持ってくれるような場を作れるかが、次の日本に課せられているでしょう。
サッカーとバスケットボールを例にしましたが、サッカーとバスケが上手いとかっこいいと言われるように、プログラミングできると、すごいというのを日本の中で浸透させる。それを推進していく一翼を担えたらと思っています。公教育の方々がやりたくてもやりづらいエデュテイメントの領域を、民間企業という立場から発信して、プログラミングはこんなに面白いし可能性があるということをしっかりと訴えていく。最初は僕らが種まきしながら、子どもたち同士でプログラミングの価値を高めて、最終的にはCtoCプラットフォームの実現に行き着くような、会社としてはそこの実現を目指していきたいと思っています」
最後は石戸が「embotの魅力は、自分がつくったロボットが『実際に動く』ところ。すごい!という感動の源泉を子どもたちに提供し続ける存在であって欲しいと思います」という言葉でシンポジウムは幕を閉じた。