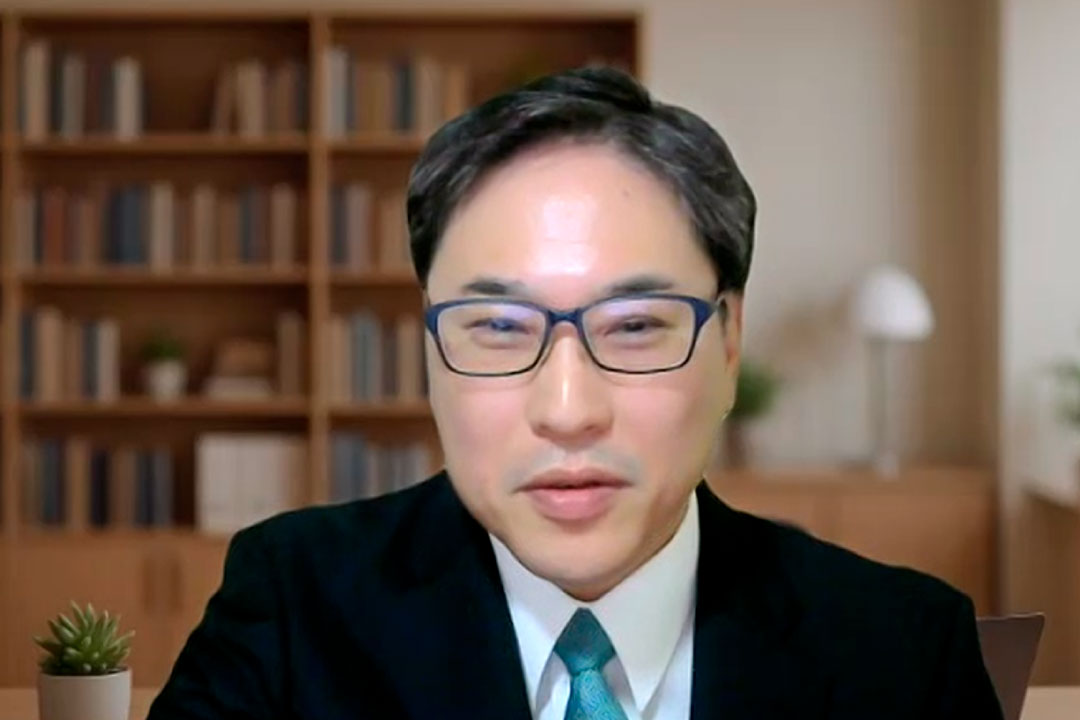概要
超教育協会は2025年6月12日、筑波大学教育推進部 教授の大庭 良介氏とデロイトトーマツグループ マネージングディレクターの吉田 圭造氏を招いて、「リカレント教育と日本発オンライン国際教育プラットフォーム『JV-Campus』の可能性」と題したオンラインシンポジウムを開催した。
シンポジウムの前半では、大庭氏と吉田氏が日本の高等教育の国際的な玄関口となるオンライン教育プラットフォーム「JV-Campus」の取り組みについて講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その後半の模様を紹介する。
>> 前半のレポートはこちら
>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画
「リカレント教育と日本発オンライン国際教育プラットフォーム『JV-Campus』の可能性」
■日時:2025年6月12日(木) 12時~12時55分
■講演:
・大庭 良介氏
筑波大学教育推進部 教授
・ 吉田 圭造氏
デロイトトーマツグループ マネージングディレクター
■ファシリテーター:
・石戸 奈々子
超教育協会理事長
 ▲ 写真・ファシリテーターを務めた
▲ 写真・ファシリテーターを務めた
超教育協会理事長の石戸 奈々子
シンポジウムの後半では、超教育協会の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問も織り交ぜながら質疑応答が実施された。
オンライン教育がさらに進展していく中で大学の在り方や価値、役割はどう変わっていくのか
石戸:「ここでおっしゃっている国際化というのは、何を意味していますか?また、JV-Campusの成功の評価軸をどこに置かれていますか」
大庭氏:「国際化は2つあると思います。学内の国際化と実際の国際的活動です。学内に関しては留学生や日本人以外も含めた学生が学習できる、研究できる場をきちんと提供できるようになっていることが大切だと考えています。
ただし、そのような場があっただけでは国際化は進みません。きちんとしたネットワークとパートナーシップのもと、実際に研究・教育の協働がなされ、新たな知の価値が生まれているような状況となる必要があるでしょう。つまり、学内の環境が整備されていること、ネットワークとパートナーシップのもとに新たな価値を生み出す環境が整っているかどうかが重要だと考えています。ただバーチャルで一方通行ではなくて両方向性を持ち、それが物理的な動きにつながっている、物理的な研究教育の成果につながっているところがゴールであろうと思っています」
石戸:「留学生に関しては、留学生の数を増やすことと、留学する方が困らない環境を整備をすることの両面があるかと思います。各々について質問ですが、実際にこのサービスを通じてどのくらい留学生の数が増えているのでしょうか。また、留学生が困らない環境という視点では、留学生が日本に来る前において日本の文化を学んだり、日本語を学んだりできるコンテンツの説明が多かったと思います。大学で提供されている授業を、日本に来る前に学ぶことで大学の単位にもなるところまで踏み込んでいらっしゃるのですか。この二点について教えてください」
大庭氏:「一点目についてお答えします。今まではオンラインを中心にした活動で増えるかなと思っていましたが、正直、増えていないです。何が必要なのかというと、オンラインでの一方通行的なコンテンツ提供だけでなく、双方向のコミュニケーションを活性化し、オンラインをきちんと活用することで、海外の学生が日本に行きやすくなる、日本に来るチャンスをもらえるという状況を作りだすことです。そこの活動をこれから強化していきたいと考えています。
二点目については、800ある日本の大学の教育リソースをクラウドで提供するような役割になりたいと考えています。全ての大学がこれだけ多様化した知の世界の中で、全ての教育サービスを提供できるわけではありません。どうしても足りないところをそれぞれ持っています。我々がクラウドリソースになって、JV-Campusに来ると足りないところを補えるというかたちで教育機関を助けることで、それが結果的に海外から来た学生も含めて日本で学ぶ学生、その先に日本国民の皆様に多様な形で教育の機会を提供できることになると考えています」
石戸:「JV-Campusのお話を伺った時に、大学ごとにコンテンツを出すのではなく、共通コンテンツの方が効率的ではないかと思いましたが、今のお話を伺うと、JV-Campusとそれぞれの大学が役割分担をしながら共有した方が良い知識をクラウドを通じて提供していくことが主眼ということですね」
大庭氏:「そうです。我々がマイクロクレデンシャルでパッケージにする際にも、ひとつのプログラムを大学ごとに作るのではなく、それぞれの得意分野を持ち寄ったものをパッケージ化する、そういったチームで作り上げていくような構想を考えています。また、この下半期から、英語で13の大学がJV-Campusを通じて単位付きの科目を提供するという取り組みを進めています。実際にJV-Campusを通じて大学の単位が取れるという状況が今年度中に実現します」
石戸:「国内外問わず大学が連携して共同で研究ができる場を作っていくお話がありましたが、実際どんな共同研究が生まれていますか。また、視聴者からも『海外の教育機関と日本の大学の連携を深めるためにどのような工夫をしているのか』という質問がきています。どのような工夫をしているのか、そして実際にどのような連携の事例が生まれているのかについて教えてください」
大庭氏:「例えば筑波大学では、パートナーであるアメリカのオハイオ州立大学と文部科学省の世界展開力強化事業に連携して取り組んでいます。インターナショナルスマートソサイエティ、いわゆるスマート社会を作るためにどうすれば良いかという教育プログラムを提供しています。JV-Campusをどう使っているかというと、まず事前に知識やスキルを身に付けるためのプレ授業をオンデマンドで勉強します。その次に、両大学の学生と先生が一緒になって教育、インターンシップを進めていくときに、リアルタイムのセミナー機能などを使ってディスカッションします。そのうえで、さらに両大学の学生が行き来をします。いきなり相手先の大学に行って何かをするのではなく、事前学習から体系立てたプログラムをJV-Campusを通じて実施することが可能になります。これがひとつです。
もうひとつの事例としては、関西大学、千葉大学、東北大学の3つの大学が合同でやっているJIGEインターンシッププログラムがあります。その中で国際的な企業インターンシップを実施するためにJV-Campusを使っています。具体的には、メタバースの事例です。2024年度も実績があります。十数社の日本企業が入って実施している実績がありますので、ただオンデマンドで勉強するというよりも、プラットフォームをひとつの場として使っていただいて、さまざまな活動をしているという例になります」
石戸:「視聴者からの質問もいくつか取り上げたいと思います。『JV-Campusを構築、運営するにあたり、最も重視した教育理念について教えてください。また、参考にされたプラットフォームや取り組みがあれば国内外問わず教えてください』というものです。いかがでしょうか」
大庭氏:「JV-Campus自身は教育機関ではないので、直接的な教育理念を掲げるというよりも、場としてどう機能するかということが大切だと思っています。その意味においては、日本の高等教育全体の国際的な玄関口として機能する、同時に日本の800ある大学のクラウドリソース的な役割を果たして大学の活動を助けるという意義が大きいです。つまり、当初から学習者個人を見ている理念ではないということが大きな特徴だと思っています。それが、結果的には学習者個人を大切にすることにつながると考えています」
石戸:「視聴者から『少子化が進むなかで日本の大学はどのようにして国内外の学習者を惹きつけるべきだとお考えでしょうか』という質問です。日本の大学が国内外の学習者、特に海外の学習者を惹きつけるために今、足りていないことや、これから先、大切になると思われることについて、ご教示ください」
大庭氏:「例えば奨学金が出せるか、先生の給料を払えるのかなど、どうしても経済的な話が出てくるのですが、その部分では海外の大学と戦えない状況だと思っています。実際に800ある大学のうち今後、健全な経営を続けられる大学が何%あるのかは大きな疑問ですし、少子化のためにより経営が厳しくなっていくことはあると思います。そんな中で、吉田さんも提示されていた学位の価値、それぞれの大学が教育プログラムとして提供する学位の価値をきちんと高めていただくことが大前提で必要だと考えています。その学位を取得することで何につながるのか、その大学にとって学位とは何か、これが一番の商品価値だと思っています。
ただし、学位にフォーカスすればするほど多様性が生まれなくなってきます。そこで、縦軸としての学位に対して、横軸としてのマイクロクレデンシャルをはじめ、さまざまな『学位の外側にある教育』をどれだけ提供できるか、学習者から見たときの選択の幅を広げていくことがとても大切だと思っています」
石戸:「学んだことを認証するものが学位だとすると、大学だけが専売特許のように認証する時代ではなくなるのではないかと思います。そうすると大学の役割を改めてどこに置くのかを真剣に議論しなければならないでしょう。このサービスを通じて国内外問わずさまざまな大学と『大学とは』、『学位とは』について議論されているのではないかと思います。国内での議論、海外での議論に分けてお話いただきたいです。今どのような方向性で議論が進んでいるのかについて教えてください」
大庭氏:「国内に関しては、今の学修内容の証明、学習成果の証明としての学位という意味合いで、より細分化した学位を出していきましょうというのが大きな方向だと思います。マイクロクレデンシャルであったり、履修証明プログラムのような形で細分化されたプログラムが、さらに細分化されるというビジョンが見えてきていると思います。
ただ、これが良いかどうかというのは、個人的には分かりません。スキル、リテラシーの細分化というのは、社会側でこそより細分化されて求めらています。だからこそ、大学の大括りな学位の話と社会側が求めている実際のスキル、リテラシーが結び付かないのが現状だと思っています。うまくできているのは数理、データサイエンス、AI、カーボンニュートラルといったところだと思います。私個人としては、細分化しすぎてしまうと、企業側には及ばない、敵わないのではないかと思っています。細分化するよりも、むしろ逆により学問の権威としての学位、学術の権威としての学位というものの価値を追求していくべきではないでしょうか」
吉田氏:「民間の観点からコメントさせていただきます。講演の最後に示した学生のニーズの多様化にどう答えるかということと、学位授与の機関としての価値はどうあるべきかという問いは、似たようなことを言っているけれども全然、違うと思っています。学位授与の機関としての価値はどうあるべきかは『着地』の話であり、学生ニーズの多様化にどう答えるかは『プロセス』の話です。学位とは、何かを修めた結果に対するもので、そこに対する価値を証明するのは、これだけ時代の流れが早くなっていると難しいと感じます。
一方で学生のニーズには、かなり臨機応変に対応していく必要があります。特にアメリカの大学はそうかなと思いますが、私がMITやボストン大学と仕事をしていた際に感じたのは、今、学生が何を欲しているのか、産業界が何を見ているのかということを大学の職員や教員が必死に考えて、それに対して自分たちのプログラムはどう可変していくべきなのかということを繰り返し議論しているということです。文部科学省が言う通り、教学マネジメントという言葉で括られるかもしれないですが、1年生で入って4年生で出た時に、どういう変化があったかを見せるのも大事です。一方で、そのプロセスでの経験を大学としてある一定レベルは担保するところまでいかないと、社会的には大学観点では厳しいのかなと思います。
先ほど大庭先生は財務の話で、厳しいかなというお話がありましたが、レべニュージェネーターをもう少し増やしていく意味で、リカレント教育はすごく注目しています。
このプラットフォームのすごいところは、ほとんどのプラットフォームで公的な要素を含んでいるところがあまりないので実際にやろうとすると、例えば高大接続と言われますが、おそらく小大接続、小学校と大学の接続はほぼないと思います。ただ小学生が軽い気持ちでどんな学びが今後あるのかを見た時に、より興味範囲の広がりなどの提供にはすごい良いものかなと思います。年齢幅を超えた時の人材の流動性や地理的な流動性ということを何かしらの価値としてまとめ上げると、そこには売りという価値が発生してくるのではないか、数年前にこれをスタートする時には大庭先生たちと会話していたことかと思います。大学はそういうところに踏み込んでいかないと従前としているとなかなか難しいのかと思います。これを一つの試金石としてやってもらいと思います」
大庭氏:「高大連携の高大接続は、スタートしています。このような活動にはオンラインプラットフォームとして距離の壁を越えて教育を提供できるという長所を生かすことができます。また、出口としてのスキルやリテラシーの習得と、学位を卒業したことによって知を創造する場を経験したということの価値は大きく違ってくると思います。だからこそ、学位に結果としてのスキル、リテラシーを求め過ぎると、場としての価値が失われていくということがあるのかなと感じました」
石戸:「視聴者から『初等中等教育でも、外国にルーツを持つ児童生徒の学びは課題となっています。国内の中学高等学校でそうした子どもたちへのアプローチはありますか』という質問がきています。低年齢に対して何らかサービスを拡張していく可能性や議論はあるのでしょうか」
大庭氏:「もちろん大学を中核としていますが、初等中等教育の話は出ています。やはりリソースも限られているので、一歩ずつ進めていくという形です。例えば高大連携に関しては、こちらから高校生フォーラムに出向いて、こういった活動をしているのでぜひこういった所で学んでみてくださいという話を、集まってきた100以上の高校にするという活動もしています。リソースが限られていて、目と手が届かないところがたくさんありますので、ぜひお声かけいただいて一緒にできるところの先導例を作っていければと思っています」
石戸:「『オンライン教育の未来はどのようになると思いますか』という質問です。アメリカでMOOCsが出てきたころと比べて、技術的にも大きな進展がありました。技術が変わると教育システムも変わってくると思いますが、オンライン教育の未来はどのように描いていらっしゃいますか」
大庭氏:「技術的な側面では、シンプルに空間と言語を超えることができるということです。これを全部超えてその場に集まることができるという意味で、突き詰めていったスタイルというものがどんどん出てくるだろうと思います。一方で対面の物理的なオフラインに対してどう存在するのかは難しい問題だと思っています。バーチャルリアリティの権威のデイヴィッド・J・チャーマーズ氏が言っているように、これは哲学的な問題だと考えています。人の認識がどうオンラインの中で変わっていくのか、もしくは、オンラインとオフラインとの関係についてマージするのか重ねて相互管理していくのか、別々のものとしてインテグリティを保たせるのかといったことも含めて、私自身も今、悩んでいます。VRはとにかくリアルを求めてマージしていこうという方向だし、それに反発している人は別々のインテグリティを持たせようとしています。ここの議論が、技術論が入ってくるといつの間にか曖昧になってしまうと思います。VRの哲学議論を見ていてもそこが整理されていないと感じています。きちんと切り分ける形で整理をしていった先に、本当の価値というのが見えてくるのかなと思います。そこは実は研究テーマになっていて難しいです」
吉田氏:「この問いは短期的な軸と長期的な軸で全く違うと思っています。この間、某ディープラーニング関連の組織の方々と話し合いましたが、長期的な視点は彼らもなかなか明確には考えられず、一方で3年くらいのスパンで考えた時にはテクノロジーおよびオンサイトのあり方は変わってくると私は思っています。まず、スキルに加えて、もう少し根幹にある感情リテラシーなどと呼ばれるものの学び方が変わってくると思います。例えば歴史を学ぶ、数学を学ぶなどは基本的にはオンラインでベースを整え、一方でオンサイトでは自分がどう感じたかなど喜怒哀楽を他人と共有します。長期的な話でいうと、大庭先生も思われている通り、かなり難しい世界に入ってくるかと思います」
石戸:「最後に、『グローバル社会で生きていくためにどのような力がこれから必要だと思いますか』という質問がきています。真の国際教育というものを考えた時に、どういう力が必要なのかということと、今後の皆さんの展望をお願いします」
吉田氏:「人間の可能性はすごくあると感じ続けていますし、そこがなくなることは絶対にないと思い続けています。学びの形態は2~3年もすれば変わってくるので、もしかしたらJV-Campusもなくなるかもしれません。一方で、感情リテラシーとインテグリティ、ここは人間がそもそも持つべきものだと思うので、ここを研ぎ澄ましていって、より対面に戻っていく可能性はあります。その際に何も情報なき中で感情のトランスファーをしたりインテグリティを模索したりするのではなくて、ベースの知識・知見というのはあるべきだと思うので、そういったところにオンラインをうまく活用するのが、今後のグローバル社会でのトレンドになるだろうと考えています」
大庭氏:「共感では自覚しているので、もう少し無意識な共鳴みたいなところでは相互貫入もあると思いますが、そこの能力を研ぎ澄ませていくことはとても大切で、今の世の中に対応して生きていくには必要なことだと思います。その中でオンラインがどういう方向へ行くかは正直、分からないです。
吉田さんの言う通り、JV-Campusは潰れているかもしれません。ただ、グローバルと言った時に、実はこのグローバルは閉じているんですよね。丸く閉じていると考えています。つまり資源は限られているのです。その限られたものをどうやって共有していくかが重要で、その時にオンラインという手法は非常に有効な手法だと思っています。その点においてはこのプロジェクトが潰れても必ず似たような話が出てくると思っています」
最後は石戸の「お二人にJV-Campusを通じて考える大学論、教育論についてのお話を伺わせていただき、ありがとうございました」という言葉でシンポジウムは幕を閉じた。