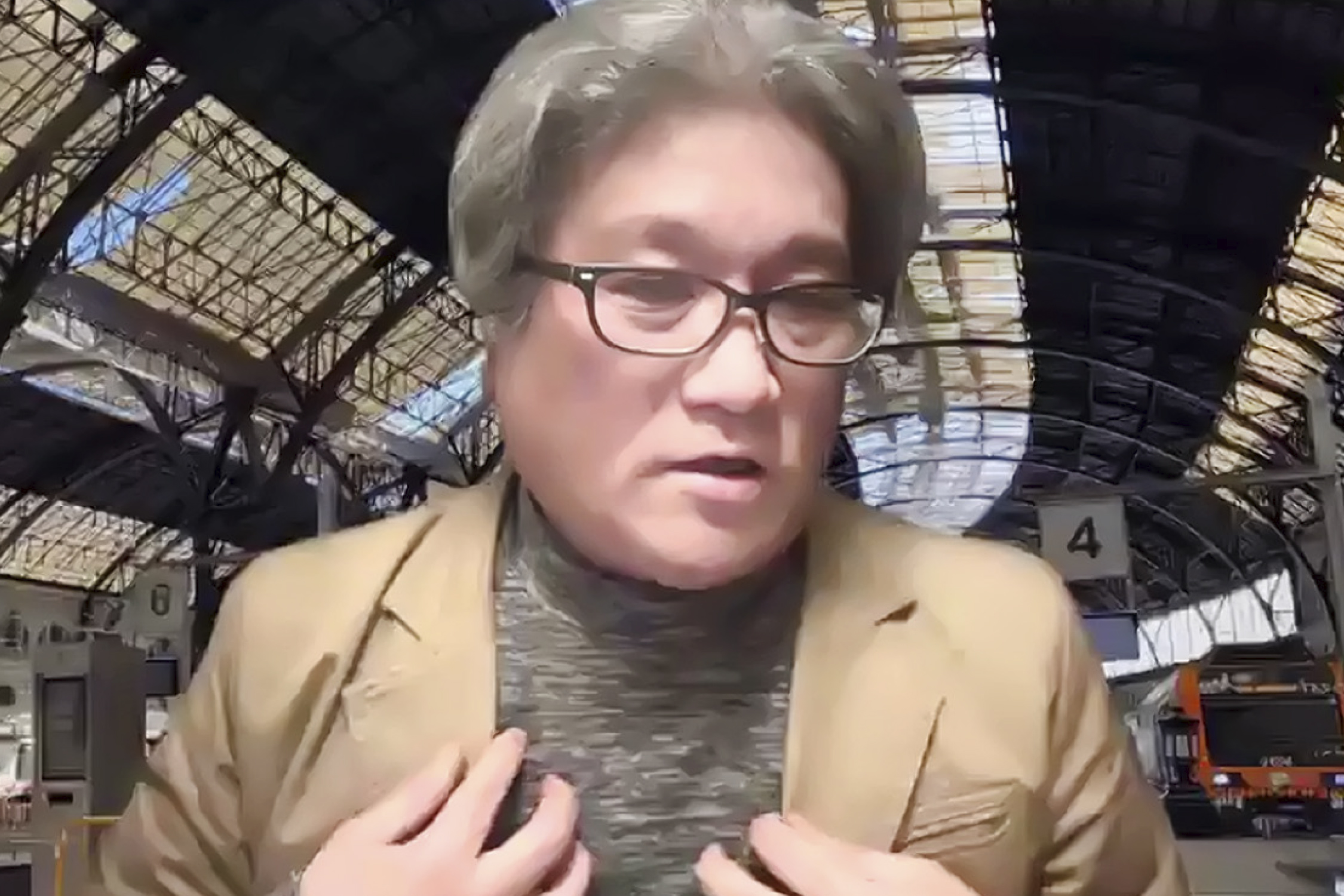概要
超教育協会は2025年5月27日、滋賀大学 学長の竹村 彰通氏を招いて、「データサイエンスで想像し創造する~滋賀大学のデータサイエンス・AI高度専門人材育成」と題したオンラインシンポジウムを開催した。
シンポジウムの前半では、竹村氏が日本におけるデータサイエンス人材育成の現状と滋賀大学の取り組みについて講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その後半の模様を紹介する。
>> 前半のレポートはこちら
>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画
「データサイエンスで想像し創造する~滋賀大学のデータサイエンス・AI高度専門人材育成」
■日時:2025年5月27日(火) 12時~12時55分
■講演:竹村 彰通氏
滋賀大学 学長
■ファシリテーター:石戸 奈々子
超教育協会理事長
 ▲ 写真・ファシリテーターを務めた
▲ 写真・ファシリテーターを務めた
超教育協会理事長の石戸 奈々子
シンポジウムの後半では、超教育協会の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。
データサイエンス・生成AIの時代に大学、そして初等中等教育に求められること
石戸:「日本はデジタル敗戦国と言われていますが、竹村先生は日本がデジタル敗戦に至った主たる要因をどう分析しているのでしょうか。そしてAI時代においてAI敗戦国にならないために、日本がデジタル敗戦の反省を踏まえて、今、すべきことは何でしょうか」
竹村氏:「日本には第5世代コンピューターもあり、スマートフォンが登場する前にはiモードもあり、世界をリードしていましたが、グローバルでスタンダードを取ることには失敗したと思います。色々なご意見があると思いますが、ハードウェア重視の傾向が強かったと思います。ソフトウェアを開発する人材を広く育ててこなかったということです。日本のウォークマンなどは成功しましたが、理系的な発想というか、デザインが少し時代に合っていなかったのでしょう。ともかく、ハードから離れたソフト分野の人材が少なかった。モノに囚われて縦割り的な技術開発なところがありました。
一方でアメリカはインターネットに注目して、そこに大きく投資して、データだけで勝負するというところに踏み込んだことが成功しました。そこで、日本との差がついたと考えています。給料体系も差があります。アメリカでは修士を卒業すると初任給が2,000万円くらいになります。だから優秀な人材が世界中から集まります。日本の企業はこの分野に関してはやはり不利な状況にあると思います。こうしたことから、日本は残念ながら遅れてしまったということです」
石戸:「AI敗戦にならないために、今、日本は何をすべきかについては、いかがでしょうか」
竹村氏:「リスキリングですね。日本のやり方にこだわらずに一生懸命勉強することです。一方で、アメリカはトランプ大統領が出てきて製造業を再生すると言っていますが、私は、全くそれはあり得ない方向性だと思っています。アメリカは、製造を他の国にやらせて、付加価値だけを取っているのが強みなのに、それと真逆のことをやろうとしています。アメリカでは今、優秀な研究者が外に出て行っている状況です。それがアメリカの力を削ぐので、日本はチャンスかもしれません」
石戸:「滋賀大学は、日本で初めて2017年にデータサイエンス学部を作られて、その後、生成AIが普及してさらにOpenAIとの取り組みを始められました。データサイエンスを始めた当初と生成AIが普及した後で、カリキュラムや教育の在り方は変更されましたか」
竹村氏:「AI手法をカリキュラムに取り入れることを順次やってきています。ChatGPTができたのが約2年半前で、その頃からデータサイエンス学部では理論を応用するような講義を取り入れ、カリキュラムを改変してきています。さらに今後2~3年でも、かなり変えていかないとならないですね。とくにプログラミング教育は大きく変わります。数学も生成AIが解けるようになって、数学や統計学でも標準的なことは『教員に習ってもChatGPTに習っても同じ』になってきています。教育のやり方自体を変えないといけないという状況に大学が追い込まれていると思います」
石戸:「滋賀大学としても試行錯誤している最中ということですね。滋賀大学では革新的に新しいものを取り入れながら、今の時代に合った大学教育をご提供されていると思います。シンポジウムの視聴者は初等中等教育に関心がある方が多いので、竹村先生が考える今の日本の初等中等教育の課題、もしくは大学教育も変わる今の時代だからこそ、大学入学前までに子どもたちに学んでおいて欲しいことがありましたら教えてください」
竹村氏:「情報Iが必修になり、その内容を見ても意欲的な内容になっていて、小学校でもデジタル的な教育を学ぶようになってきています。タブレット端末が配られるなど進んできていると思いますが、一方で教員の力不足が課題になっていると思います。また、高校に関しては大学の入試が文系、理系的なイメージがまだ強く、あまりこれからの時代には合っていない状況です。入試を変えるのは難しいのですが、もっと文理融合的な教育をしていかないといけないと思います。文系の大学に行くと、数学は途中でいいや、となってしまい、逆に理系に行く人は技術者寄りになってしまいますが、社会の在り方自体が変わってきているので、理系・文系という人材像は良くないと思っています。そこは課題だと思います」
石戸:「大学のカリキュラムがこれから大きく変わらなければならないというお話がありましたが、大学そのものの存在意義も問われるのではないかと思います。入試ひとつとってみても、本来であればダイナミックに変わらなければならないのではないでしょうか。日本の大学全体を見て、大学はこれからどうあるべきなのかご意見をお願いします」
竹村氏:「大学では、ノートパソコンを開いて教員の言っていること、分からないことをChatGPTで聞いている学生も多いです。そういった変化がありますが、大学の教育はその技術の変化に合わせなくてはいけない。
また、大学の在り方は、もっと社会と密接になることです。先ほど言ったように学び直しの機会を大学が提供することで、学生から見たら年齢が上の社会人が混ざります。そういう多様性があって世代間の交流があるのが望ましいです。そういった変化は徐々に出てくるのではないかと思います」
石戸:「企業との繋がりでは、先ほど累計400社以上と連携しているというお話がありました。企業が大学にお金を払ってリスキリングを依頼し、それを大学としても学生や研究者の学びとして活用しているという構造ですか」
竹村氏:「もちろんそうです。日本の企業は、アメリカの大きな大学や中国の大きな大学には結構なお金を出しますが、日本の大学には出さないという傾向があります。きちんと日本の大学にも出してくださいとお願いしています。もちろん大学側も企業側のニーズに合わせたプログラムを提供しなくてはいけないです。大学院では、派遣された人は勉強に来るというより、仕事の一部として、企業の直接の課題を解くために来るというかたちです。そして、そうした企業には、日本の大学をもっと支えてくださいとお願いしています」
石戸:「日本も企業に余裕があった時代は、就職してからOJTで育成することが成立していましたが、今はその余裕もなく、その役割を大学に求められていると思います」
竹村氏:「データサイエンスやAIに関しては、企業内でのOJTでは難しいです。大学を人材育成に利用しないと、社内だけではできないです。社内の固有の技術だけで製品を作っているのだったら企業に入ってから勉強すれば良いのですが、それだけだと大きなイノベーションに対応できないので、やはり企業側も社内教育だけでは時代の変化に対応できないようになってきていると思います。企業間の連携もあるし大学との連携もあると思いますが、そこを広げていかないといけない時代になってきていると思います」
石戸:「視聴者から『日本のAI、データサイエンス人材育成には、海外の先進事例と比較してどのような課題や可能性があると思いますか』という質問です。そして最後に、今後の展望をお聞かせください」
竹村氏:「データサイエンス人材が社会で活躍できるように企業側も待遇を考えていただきたいと思います。アメリカはちょっと特殊ではありますが、優秀な頭脳を集めるという意味では非常に柔軟です。日本はもう少しジョブ型採用など工夫しなくてはならないと思います。滋賀大学はデータサイエンスやAIに関しては企業と連携した実際的な形で拡大していますが、日本の大学全体的にそういう形で社会との連携を深めて、社会から投資していただけるような形でさらに改革していくことが大事だと考えます。これを最後のメッセージとさせていただきます」
最後は石戸の「滋賀大学が、社会が抱えている課題、そして産業界の需要を捉えた理想的な産学連携モデルを構築されていることがよく分かりました。人材不足という視点を踏まえると、滋賀大学のモデルが全国の大学に広がっていくと良いと思います」という言葉でシンポジウムは幕を閉じた。