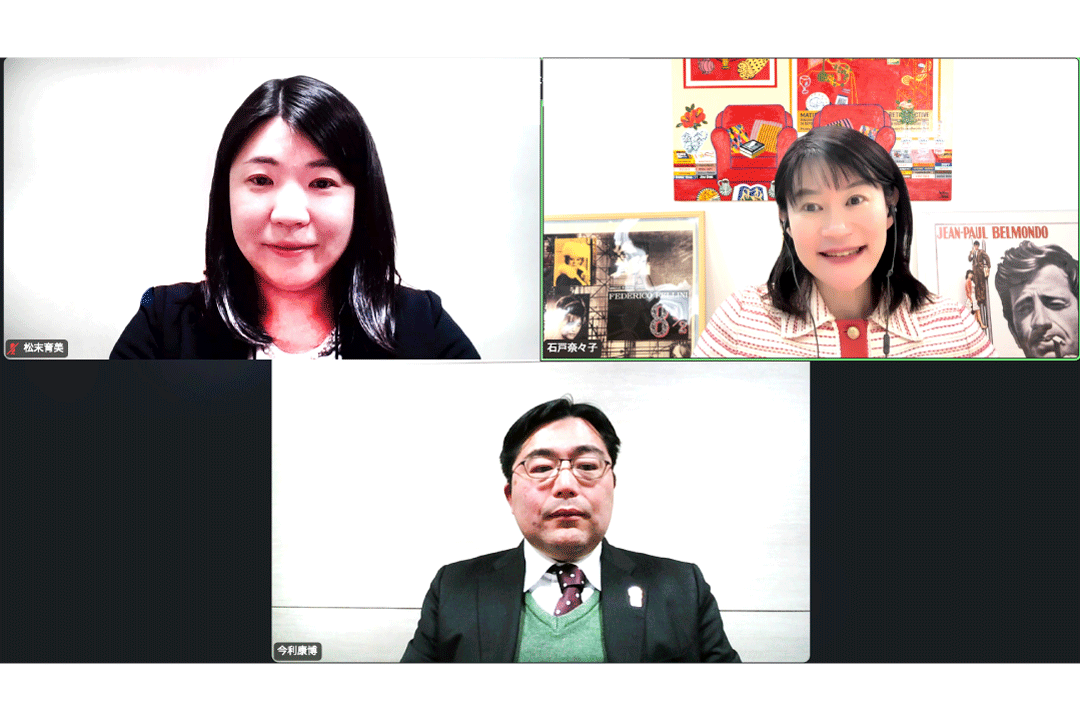概要
超教育協会は2025年2月5日、大阪市総合教育センター 教育振興担当 ICT推進グループ 総括指導主事の今利 康博氏、コニカミノルタジャパン株式会社 ICW事業統括部 教育DX事業開発部 副部長の松末 育美氏を招いて、「生成AIを使って授業が変わる~個別最適な学習をめざして~」と題したオンラインシンポジウムを開催した。
シンポジウムの前半では、今利氏が大阪市の小中学校での生成AIの活用について事例を交えて紹介し、松末氏が学校教育向けソリューション「tomoLinks」の機能を説明した。後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その後半の模様を紹介する。
>> 後半のレポートはこちら
>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画
「生成AIを使って授業が変わる~個別最適な学習をめざして~」
■日時:2025年2月5日(水) 12時~12時55分
■講演:
・今利 康博氏
大阪市総合教育センター 教育振興担当 ICT推進グループ 総括指導主事
・松末 育美氏
コニカミノルタジャパン株式会社 ICW事業統括部 教育DX事業開発部 副部長
■ファシリテーター:
・石戸 奈々子
超教育協会理事長
 ▲ 写真・ファシリテーターを務めた
▲ 写真・ファシリテーターを務めた
超教育協会理事長の石戸 奈々子
シンポジウムの後半では、超教育協会の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。
小中学校の授業で活用できるtomoLinksの生成AI機能に関心が集まる
石戸:「tomoLinksでは、AIに学習させるデータを絞ることによって安全性を確保していると聞いています。どういう学習データを学習させ、どういう配慮をしたのか教えてください」
松末氏:「まず、子どもが対話した内容については、全く学習させていません。子どもがスムーズに対話できるように、教育的な観点から子どもが有害なキーワードを入れてしまったときに会話しないようにするといった設定をし、生成AIが先生のようにスムーズに会話できるようなデータをプリセットしています」
石戸:「個別最適化された情報を提供するために、教材にひもづいたデータの取り方ではなく、教材コンテンツ横断型で、なおかつ学力調査のデータや教材の学習データも活用されていると伺っていましたが、その認識で正しいでしょうか」
松末氏:「正しいです」
石戸:「具体的にどういうデータを学習させたのか、そのデータを学習することの同意を得るところでハードルはなかったのでしょうか」
松末氏:「tomoLinksの中でキャラクターが子どもたちと会話するところでは、tomoLinksの中に入っているドリルを解いた子どもたちのフィードバックを活用しています。子どもが間違ったり、つまずいたりしているところを説明するような内容で会話するように設定しています。子ども自身がドリルを解いたとか、正答したといったデータから、キャラクターとの対話の流れなどが変わっていくようにしています」
石戸:「視聴者から『学習指導要領との整合性はどのように確保されているのでしょうか』という質問もきております。いかがでしょうか」
松末氏:「いろいろな先生に監修をしていただいています。その先生方が学習指導要領に沿って指導されているところで、学習指導要領に準拠した対話ということになっています」
石戸:「今回、年齢制限を外されたということが特徴の一つだと思います。例えばChatGPTも年齢制限がありますが、大阪市としては何歳から生成AIを活用した授業に取り組んでいるのか、年齢制限を外すに当たってどのような配慮をしたのでしょうか。実際に外してみていかがでしたか」
今利氏:「今回、住吉小学校では小学2年生から取り組んでいます。初めての挑戦でした。その中でしっかりと子どもたちに、生成AIは道具だということを教えることが大切だと思っています。人格を持たせないようにするということが非常に重要で、そこを先生が情報モラル教育の中で教えるとともに、使うときに必ず説明するように徹底しています。子どもたちもそれを理解しながら生成AIを使っていたと思います。
tomoLinksに関しては特に年齢制限は特に設けられていないので保護者同意や未成年の利用同意等は必要ないですが、先生側の指導は一定程度必要と考えています」
松末氏:「AzureのOpenAIのAPIを使っています。ChatGPTをそのまま使っているのではないので、年齢のハードルは特にありません。とはいえ、子どもが使うというところにおいては有害なワードをブロックするところは必要です。そちらには必ずフィルターを用意しています」
石戸:「学力調査のデータを学習させるときには、何人ぐらいの何年分のデータを活用されているのでしょうか」
松末氏:「今回は大阪市での実証ということで、学年を絞って、1年間のデータを活用しています」
石戸:「何人分のデータですか」
松末氏:「実証校のため100人程度です。学年も絞っています」
石戸:「コンテンツ横断型とすることで個別最適化を実現していることが特徴ですが、対話においてどのぐらいの差が出ていますか」
松末氏:「多くの事例があるわけではないですが、一部の子どもの使い方を先生にヒアリングすると、これまではGoogleだけでは難しい漢字が入っていると諦めてしまった調べものなどを、生成AIには簡単に聞けるという声があるようです。分かりやすいから会話してみるというような使い方の差はありました」
今利氏:「学力と今回の生成AI活用との関係をどう分析すれば良いのかを判断するのは大阪市だけでは難しいものです。授業の中で、どう子どもたちが変化したのか、変容していったのかという読み取りが重要ではないかという意見もあります。令和7年度も引き続きこの生成AIパイロット校は進めていきたいと考えておりますので、質問にもありました評価の方向やエビデンスに基づいた分析については、引き続き来年度もどのような方法があるか模索していきたいと考えています」
石戸:「今回の生成AIの評価軸や評価方法について教えて下さい」
松末氏:「評価軸をどのように取るかについてもこれからの取り組みだと考えています。学力なのか、情報活用能力なのか、興味関心が膨らんだといったことなのか、さまざまな評価軸が考えられます。まずは、子どもたちがどういう反応を示すのかといったことを考えて、学校と一体で動いているというかたちです。まだ、始まったばかりということで令和7年度も引き続き実施しますので、定量的なエビデンスをだしていきたいと思います」
石戸:「前回、ご登壇のときの質疑の際に、指標は『良い授業は何か』の定義によるという議論がありました。そのときには、そこはこれから考えていくというご回答だったと記憶しています。それから3年が経ち、いまは良い授業をどのように設計されているのかも気になり、評価について質問させて頂きました。tomoLinksがリリースされて3年が経ち、開発の指針など何か変化はありましたか」
松末氏:「今日、発表した内容は子どもたちの教育データの活用というところが共通している部分です。ドリルで活用する、生成AIとの対話をしながらドリルを提示するときに活用するということなどです。いろいろなサービスとして拡張しながら進めているところが現状です」
石戸:「視聴者から『対話内容を学習しない場合、個々への最適化はあまりできないようなイメージが持ちますが、そこにはあまり重きを置いていらっしゃらないということでしょうか。学習データの読み込みなどでカバーできるものでしょうか』という質問がきています。いかがでしょうか」
松末氏:「対話内容は学習しないのですが、学習ツールとしてもご活用いただいています。tomoLinksドリル一体型、協働学習ツールなども入っているので、子ども自身の教育データから子ども自身の理解度やつまずきポイントが分かってくると思います。それらのデータをAIが判断して子どもたちとの会話を変えていくことができます。あたかも先生が普段の小テストの採点などから、『この子は、ここが分かっていなかったのだ』と把握するようなことをデジタル化するイメージです。対話内容だけでなく教育データを一体として活用することで、子どもにフィットした対話ができるようになると思います。まさしく仮説検証の真っただ中です」
石戸:「視聴者から『これは先生方への教育になりますが、プロンプトは適切な使い方が不可欠で、先生方のこの指導をどのような方法で実施されていますか』という質問です。いかがでしょうか」
今利氏:「今回のtomoLinksの導入にあたっては、事前に先生方に生成AIの活用も含めた研修をしました。その中で質問を受けながら、また月に何回かコニカミノルタジャパンにも訪問してもらい先生方の支援をしていただいています。このように、まずは先生方自身で生成AIについての理解を深めていただきます。そこが重要です。
その他にも大阪市では夏休みの研修をしたり、さまざまな事例をナレッジ共有サイトで共有したり、使い方の方法や指導案も含めて共有したりしています。そういった取り組みで先生方に理解を深めていただいています」
石戸:「視聴者から『親しみやすい対話型生成AI機能は、子どもからの視点や使いやすさが重要だと思います。子どもの視点をどのように把握してサービスに取り込んだのかを教えて欲しい』という質問です。いかがでしょうか」
松末氏:「実証校の先生、教育委員会の方々にも見ていただいてフィードバックをいただいております。実際、私も学校に行き、子どもたちの声を聞くなどしています。『これ、使い難いのだけど』などと子どもの素直な意見をかなり聞くことができます。それらの意見を参考に、サービスを月単位でアップデートしているところです」
石戸:「保護者の同意に関する質問がたくさんきています。先ほどtomoLinksは年齢制限がないため保護者の同意は不要であるという説明がありましたが、『保護者の同意はどのように周知し、どのように同意を取っているのか、取っていないのか』、『保護者から使わせたくないというような意見はなかったのか』、『保護者のみならず、各社とのプライバシーデータ、個人情報の扱いについてどのように説明して対処しているのかについて知りたい』という声が複数上がっています。いかがでしょうか」
今利氏:「まず大阪市側ですが、今回のtomoLinksは、年齢制限で保護者同意が必要ありませんので特に取っておりませんが、今後、例えばChatGPT、Copilot、Geminiなどの生成AIを使う場合には保護者同意が必要になります。現在、我々も文部科学省の生成AIガイドラインを見ながら保護者同意の文例作成に取り組んでいます。
今回は4校ともに保護者から生成AIに対して否定的な意見はなく、逆に最新の技術を授業に取り入れてくれて嬉しいといったご意見がありました。保護者も家庭で生成AIの使い方を教えないとならないと思っているケースもあり、そこを学校が指導してくれるので大変助かるとか、そういう前向きな意見が多かったと感じています。
個人情報やプライバシーデータについては、今回は子どもたちの名前などの登録は一切していません。全部番号を登録していて、学校もその番号と名前を別の紙と照らし合わせながら活用しています。個人情報を入力するところはなく、実際に生成AIに入力するときにも、個人情報は入力しないということを徹底しています。引き続き、大阪市としても、生成AI活用に関しては個人情報などを入れないで使うという方向性で進めていこうと考えています」
松末氏:「保護者同意のところは、弊社にもどうしたらよいのかというお声をたくさんいただいています。基本的には教育委員会や学校側のご判断で、もし心配であれば保護者同意を取ったほうがよいと思います。もちろん当社からも保護者同意のひな形のような文面は提供可能です。もし必要であれば弊社からご提供いたします」
石戸:「生成AIの教育での活用に関して、本日、素晴らしい良い声をたくさんいただきましたが、『実際に見えてきた課題、さらにはもっとこういう可能性があるのではないかということについて知りたい』という質問がきています。いかがでしょうか」
松末氏:「子どもや学校の先生にヒアリングしていますが、やはりチャットに何を聞いたらよいのか分からないという子どもが多いのが現状です。何を聞いたら分からないというような、最初の一歩のところにおいて、子どもたち向けの研修のようなものが必要なのではないかと感じているところです。弊社としても手厚くサポートしたいと思っています。これは子どもも、先生も含めてだと思います」
今利氏:「生成AIを活用するうえでの課題は、例えば歴史上の人物であれば、あくまでも生成AIが生成した内容であるということを常に子どもたちに話していくことが必要です。つまり、すべてが事実ではないということをしっかりと子どもたちに指導することが大切だと思っています。
実際、小学生の子どもたちが一番はじめに生成AIと出合う場面でおもしろい取り組みだと思ったのは、『しりとり』です。しりとりは最後に『ん』がついたら駄目なゲームですが、結局、しりとりのルールを生成AIがきちんと理解できなくて、必ずどこかで『ん』がついて終わってしまうのです。生成AIと言いながらも完璧ではないということを子どもも理解できるのです。このように、ファクトチェック、ハルシネーション、バイアスなど、生成AIにはいろいろな課題があります。そこを授業の中で取り組み、大阪市としてもそれらを含めた授業モデル案を作っていこうと考えています。学校からもモデル案があればよいというご意見もいただいております。モデル案に取り組んだ後、生成AIに入っていただく流れをしっかり作っていきたいと考えています。子どもたちは個別の課題に応じて生成AIを活用できるので、自分のペースで取り組めると思います。友達との対話学習をすると授業に関係のないおしゃべりが増えます。生成AIにはそれはないので自分のペースで取り組めるのが嬉しいという声がありました。そのような授業展開が確保できるのが良いところだと思います」
石戸:「Q&Aを読まれて今利さんが引用してくださった視聴者からの質問は、『ファクトチェックが必要だと伝えることはできるが、実際にどのようにファクトチェックさせることへの指導についてどうされているのか』、『歴史上の人物の学習データは、何を参照しているのですか。実際に学習データは、本人の人格や思想とかけ離れたものになっていることはないのか。もしくは、歴史上の人物で偏った思想を子どもたちに伝えることになる可能性があるのではないのか、それをどのように防いでいるのか』というものです。松末さんから、補足の回答がありましたらお願いします」
松末氏:「ファクトチェックができる子どもたちの年齢になったらできますが、『これって本当なの?』ということを確かめることも学習の進度に応じて必要だと思います。さまざまなお声は聞いていますが、どうしてこういう回答をしたのかというエビデンスも含めて出してくれると嬉しいということを聞いております。そこはシステムとして検討したいところではあります」
今利氏:「私から補足です。生成AIに限らず、例えば世の中にあるSNS、インターネット、いろいろなところで事実とは違うことが情報として溢れかえっています。インターネットを使ったり、SNSから情報を集めたりするうえでファクトチェックは必要です。そこを先生方や我々が意識しながら授業の中に取り込んでいくことが大切です。
例えば偏った思想などについてインターネットで検索すると、その検索に基づいたいろいろな情報が勝手に提供されます。子どもたちに、しっかり指導することが重要だと思っています」
石戸:「ありがとうございます。おっしゃるとおり生成AIのみならず、フェイクニュースやフィルターバブルの件は、対処方法について、子どもたちにも学習を通じてしっかりと伝えていく必要があると思います。
最後に『今回、大阪市でしっかりと実装されていますが、実際に自治体に導入するにあたってはどのようなハードルがあるのか、ほかの地域に展開していくときにどのような留意点があるか』という質問がきています。最後に展望も含めて教えてください」
今利氏:「大阪市としては、文部科学省が2024年12月25日に出した生成AI利活用に関するガイドラインを再度確認しながら、どのようにして大阪市全体に広げられるかというところを内部で検討しているところです。やはり先生方に慣れていただくことが大切です。まずは校務や業務の中で生成AIを利用していただくところがスタートになると考えています。
当然、今回のパイロット校は、そうしたハードルを乗り越えているのですが、実際、授業にどう使うのかというところはtomoLinksだけではなく、あくまで先生の代理入力という形ではありますが、Copilotを使ってどんな授業ができるかという検証もしています。それらを一つの手引きという形にまとめて先生方に展開していこうと思っています。そして、しっかり研修もしながら大阪市全体に広めていきたいと考えています」
松末氏:「まだ生成AIを使ったことがなく、『生成AIとはどんなものか?』という初歩的な疑問をお持ちの先生もいらっしゃると思います。生成AIとは何かということを子どもに教えなければいけないですが、先生自身もそういった基礎知識は普段の業務効果を皮切りに身につけていくことが多いようです。そこは当社もサポートもさせていただきたいと思っています」という松末氏の言葉でシンポジウムは幕を閉じた。