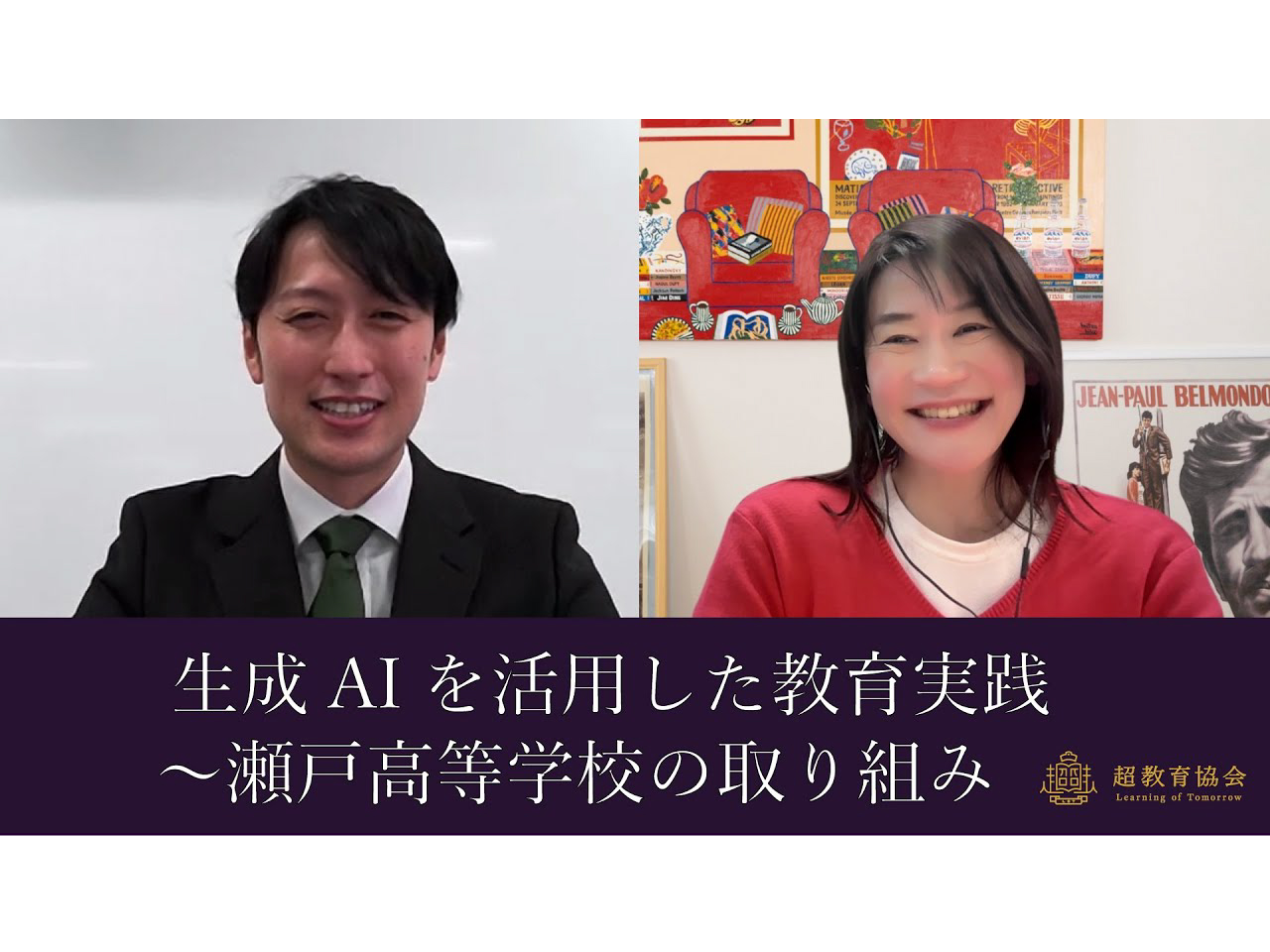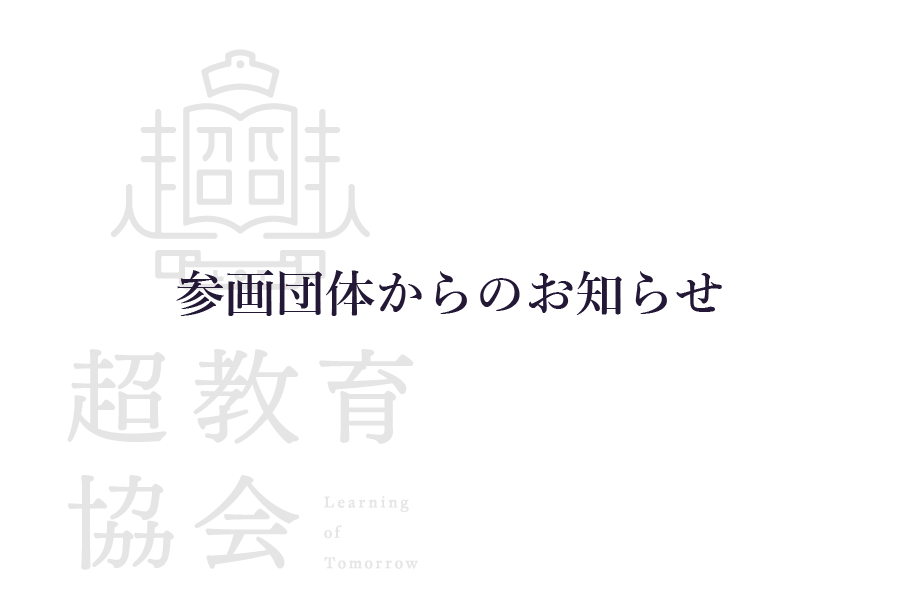超教育協会では、2018年12月1日、東京・本郷の東京大学で「超教育展」を開催しました。「VR×教育公開型ワーキンググループ(WG)」では、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)が教育にもたらす可能性について8人の専門家がプレゼンテーションをし、その後に、超教育協会・理事長の石戸奈々子がモデレータとなって、ディスカッションを実施しました。その様子を紹介します。
リンク:VR(仮想現実)は教育のあり方をどう変えていくのか ~「VR×教育公開型ワーキンググループ」レポート(1/3)~
教育を変えるVR(仮想現実)の可能性 ~「VR×教育公開型ワーキンググループ」レポート(2/3)~
VRは教育の分野に本格的に普及・定着していくのか

合計8名の専門家によるプレゼンテーションの後は、石戸がディスカションを進行しました。石戸は、まず、公開型ワーキンググループを開催した目的として、「VRを教育に取り入れる」、もしくは「VRが教育に入る」ということがどういうことか、「その共通認識をこの場で作りたいと考えていました」と話しました。
石戸は、VRにはさまざまな可能性があるにも関わらず、「聞こえてくるのは、『歴史を、臨場感を持って学べるようになる』といったことばかりのような気がしていました」と指摘。続けて、「イメージがすごく矮小化されたまま、VRを活用した教育の議論がなされている印象を持ちます。そこを変えたいなという思いで、今回のワーキンググループを開催しました」と説明しました。
そうしたワーキンググループ開催の主旨に沿って、ディスカッションは進められました。石戸は、専門家のみなさんに質問を投げかけ、それに対して、フリートーク形式で回答するという形で進行しました。
最初の質問は、「2016年がVR元年」とされたことに関するものでした。VRのブームはじつは2回目で、90年に第一次ブームがあって、2016年以降、現在まで第二次ブームが続いています。石戸は、「今回は、ブームではなく『定着する』かどうか」を質問しました。
それに対し、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科准教授の南澤孝太氏は、「定着の仕方が重要です」と回答しました。現在のようにVRが先端的なテクノロジーとして注目され続けているうちは、本当の定着とは言い切れないとも考えられます。南澤氏は、「VRが『VRだと意識されないレベル』まで普及することがポイントにある」と意見を述べました。インターネットのように、インフラと呼べるまでに普及するかどうかが、定着かそうでないかの分かれ目になるといえそうです。
ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社日本担当ディレクターの大前広樹氏は、もし仮に「VRが社会に必要のない、ただのレクリエーションの技術だとすると、ブームが終わったら『あんな技術もあったね』と昔話になってしまうでしょう」と切り出しました。ところが、VRを活用した教材は、学校教育の現場だけではなく、建築業界などでは「なくてはならないものになっています」(大前氏)。その意味では、「定着しつつあり、定着すると考えています」と自らの考えを示しました。
海外と比べて「遅れている」とは言いがたい 日本でのVRの普及度合い

次の質問は、「VRの教育利用は進展するか」、そして、VRの教育における「世界と日本との比較」でした。この質問に対し、最初に回答したデジタルハリウッド大学学長の杉山知之氏は、「VRの教育利用は、進むかどうかではなく、『進めないとならない』と考えています」と発言しました。そして、「放っておいては進まないので、やはり、進めたい側からアクションを起こしていかないとならないと思います」との見解を示しました。
一方、東京大学大学院情報理工学系研究科講師の鳴海拓志氏は、海外と日本におけVRの利用状況について言及しました。鳴海氏は、「世界でも中学校や高校の現場で活用しているかというとそうでもないと思います」と説明。海外と日本で、それほど
大きな差異はないようです。
続けて、鳴海氏は、ジェレミー・ベイレンソン氏の「VRは脳をどう変えるか」という書籍を引き合いに、「アメリカンフットボールのNFLの選手がVRを活用したトレーニングをすると戦績が全然違ってくるといったことがわかってきています」(鳴海氏)と紹介しました。VRの活用には、やはり費用がかかるため、プロスポーツの分野など、VR活用に予算をかけられる分野での活用が進んでいるようです。
また、グリー 開発本部XR事業開発部部長の原田孝多氏は、「企業でも、セクハラやパワハラの教育や研修ではVRが導入されています。相手の気持ちになって考えることができる機能が活用されています」と説明しました。原田氏によると、「必ずしも、日本が遅れているという感覚は持っていません」ということでした。
AI(人工知能)の気持ちをVRで体験 長い時間を経た「経験知」を短時間で知る

続いては、具体的に教育に利用するとしたら「どういう利用・活用が想定できるのか」について、参加者の考えを、ひと言ずつ発表していただくというものでした。
これに対する回答でユニークだったのは、東京大学先端科学技術研究センター教授の稲見昌彦氏の回答でした。稲見氏は、「VRで人の気持ちを体験する活用はいろいろとされているが、『AI(人工知能)の気持ちを理解する』という発想は聞いたことがない」と話し始めました。
稲見氏によれば、例えば将棋のAIも、いろいろと困ったり、考えたりしているとのこと。実際に、AIの探索空間が広がることもあるそうです。「あれこれ考えて、悩んでいるAI、コンピュータの気持ちになれると、プログラムを書くときもコンピュータの気持ちになって、わかりやすく書いていこうとなるでしょう。つまり、プログラミング教育にVRでの体験を活用するということが想定できます」(稲見氏)と、独特なアイデアを披露しました。
さらに、大前氏は、テニスやバドミントンなどスポーツの分野で、「自分とダブルスを組む」というアイデアを紹介しました。石戸も「ダブルスの相手が、自分のどのプレイに腹を立てているかがわかって(笑)、さらに、そんなプレイをしていた自分にも腹が立って、となりますね」と話し、自分を客観視できるVRの効果を強調しました。
一方、南澤氏は、VRで「経験知」を増やしていくという活用について言及しました。南澤氏は、まず、本の効用について「数百年の歴史を扱った本を読むと、わずか数時間で何百年もの時間を『圧縮して』体験できます」と説明。人間は本を読むことで、過去の人の経験を本の中で体験して経験知を得ていきます。「VRにおける時間が、日常空間の時間の進み方と同じだと、何かを体験するのに同じだけの時間がかかってしまいます。それでは自分が得られる経験知が増えません。そこで、本のように実際の時間よりも、はるかに速いスピードで体験できるようにし、それが積み重なって経験知となるような活用が重要になります」と説明しました。
また、南澤氏は、「スポーツのルールの設計者になる」という体験、視点を変えるという体験でができることでのVRの有効性を説明しました。南澤氏によれば、既存のスポーツのルールを変えることで、プレーヤーがどういう動きになるか、もしくは町の条例を設計することで人がどう行動を変えるかなど、「俯瞰的に見ることで、ルールの意味合いもわかるようになります。その上で、さらに、どういうルールにすればもっと幸せになれるのかを考えていくこともできるでしょう。そういった発想をもった人材がそだっていかなくてはならないと考えています」と意見を述べました。
教育でも「超教育」の分野でも さまざまな視点での活用に期待

石戸からの最後の質問は、VRの教育での活用のために「今後すべきこと」、そして、「VRの未来はこうなると思うこと」でした。グリーの原田氏は、「投資しやすい環境」の整備としました。つまり、VRのさらなる開発、品質の向上では、やはり費用がかかるので、利用や活用することでメリット享受する側からの投資が不可欠であるといいます。
この意見に対し、石戸は、「産業界も含めて新しい教育を考えましょうというのが超教育協会です。VRの普及においても、ぜひ産業界から協力を得たいと考えています」と目指す方向性を示しました。
稲見氏も同じように、初等・中等教育を変えることには時間がかかることを伝えつつ、「公教育だけではなく、塾やメーカーのコミュニティなどとも連携しながら変えていく、『超教育』の取組みが必要かもしれません」と見解を示しました。
また、VRの未来はこうなるという質問では、大前氏が「教材のスマホ」という独特の表現をしました。「昔で言えば電卓やノートが会社員の必需品でした。それがパソコンになって、今はスマートフォンになりました。VRも、例えば理科の実験器具など学校で必要な教材を全て集約したような、VRはひとつあれば、全部できるようになる、そんなアイテムになるではないでしょうか」と語りました。
「人生多チャンネル化」と示したのは稲見氏です。現実と仮想の2つの人生があって、さまざまな人生を歩めるようになるといった未来を説明しました。
さらに杉山氏は、「新人類」と。「これからの人たちは、『VRありき』の人類になるということです。98億人の人間がいたら、『98億通りの現実』、それぞれの人にとっての現実があるような世界ができてくるでしょう。その世界で暮らす人たちはまさに新人類です」。その他にも、南澤氏の「本であり、空間であり、友達であり」という表現もありました。
最後に石戸は、この公開型ワーキンググループによって、VRに対する固定概念的なイメージが少しでも払拭され、もっと可能性のあるツールとして教育分野をはじめ、教育を超えた分野でも活用されることへの期待を語り、ディスカッションを締めくくりました。