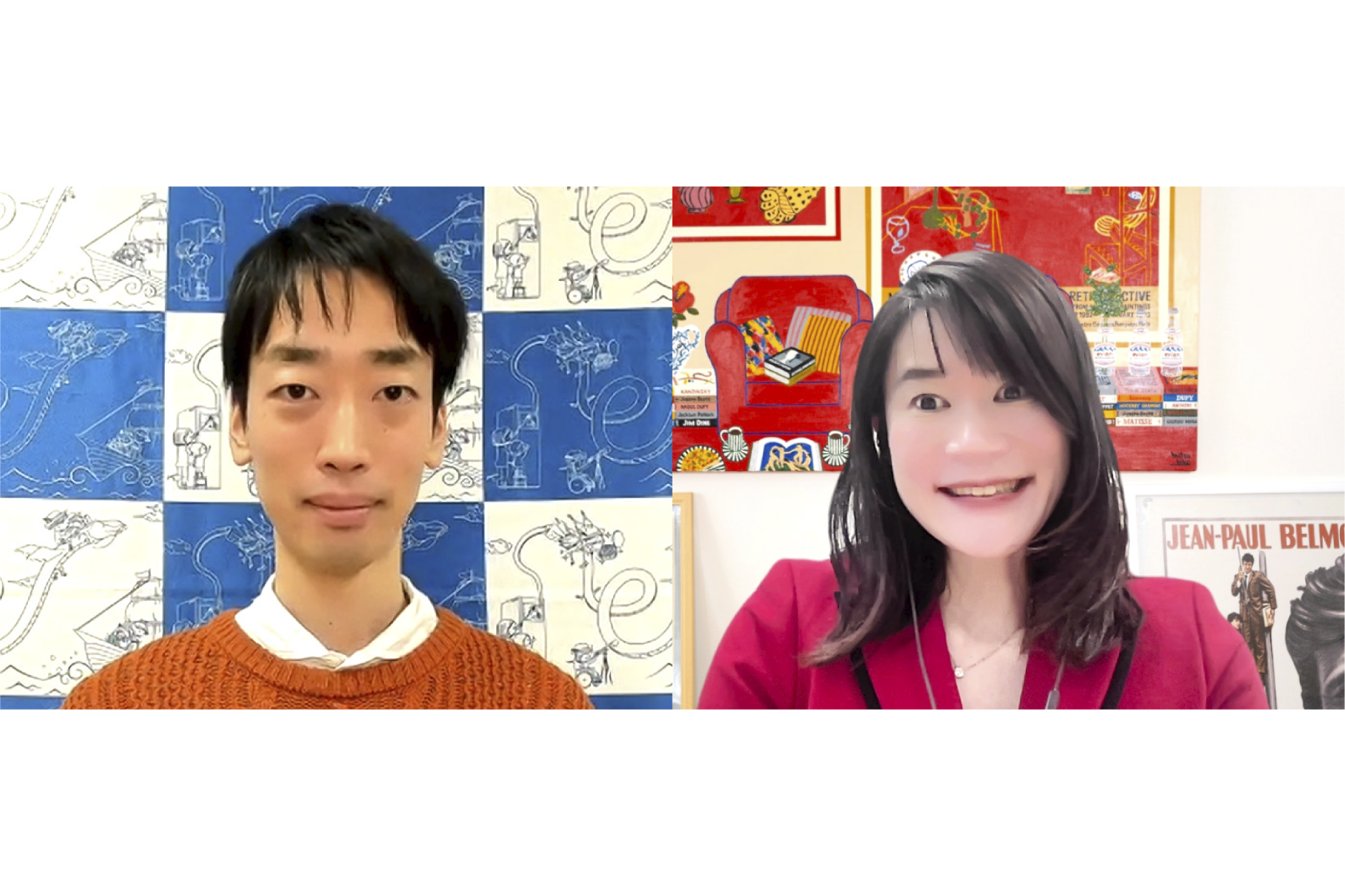概要
超教育協会は2024年12月4日、NPO法人「はびりす」の作業療法士である奥津 光佳氏を招いて、「すべての小中学校に『学校作業療法室』 飛騨市の挑戦が未来を照らす」と題したオンラインシンポジウムを開催した。
シンポジウムの前半では、奥津氏が「学校作業療法室」の取り組みについて講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その後半の模様を紹介する。
>> 前半のレポートはこちら
>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画
「すべての小中学校に『学校作業療法室』 飛騨市の挑戦が未来を照らす」
■日時:2024年12月4日(水) 12時~12時55分
■講演:奥津 光佳氏
NPO法人はびりす 作業療法士
■ファシリテーター:石戸 奈々子
超教育協会理事長

▲ 写真・ファシリテーターを務めた
超教育協会理事長の石戸 奈々子
シンポジウムの後半では、超教育協会の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。
「学校作業療法室」の今後の取り組みにも興味・関心が多く集まる
石戸:「子どもたちの自己効力感が高まる形での支援をし、なおかつ、学校の先生、それから保護者の方々の子どもたちとの向き合い方の変化も生まれていることで、非常に素晴らしい取り組みだと思いました。
飛騨市として『学校作業療法室』を作るにあたり予算などもつけていると思うので、その決断に至る経緯が気になります。視聴者からもこのような質問が届いています。『学校の中に外部組織のための部屋を設けてもらうに至ったのはすごいことだと思います。これまでの折衝や議論の軌跡やキーパーソンの存在などがあれば伺いたいです』といったものです。効果があるとはいえ、コストもかかりますので、学校作業療法室がどういう経緯を経て設置に至ったのか、教えてください」
奥津氏:「学校作業療法室が設置されるに至った経緯についてご紹介します。飛騨市には行政の中の横断型組織である地域生活安心支援センター『ふらっと』があります。この組織は保護者、子どもから成人までさまざまな市民の相談事を受ける組織です。約5年前から始まり、最初は保護者から子どもの行き渋りや不登校、勉強が難しいなど、あるいは友達とのトラブルが絶えないといった相談がありました。その保護者への相談にお答えしていく中で、『学校とも連携を取れるようになったほうがいいね』と考え、学校とのつながりができ始めました。
そういった保護者からの相談に対して学校にお答えしていく中で、だんだん学校からも相談が届くようになりました。読み書きが難しい子どもや教室に入れない子ども、あるいは喧嘩が止まらない子どもに対して一体どのように接していったらよいのかという学校側からの相談が増えていき、そういった相談に対して作業療法士が直接、学校にお邪魔して先生と相談や環境の調整を行うことが増えていきました。そういった学校の先生たちの認識の中で、『作業療法士は便利だ』と思っていただくようになりました。
飛騨市では月1回の校長会があり、その中で『実際に作業療法士が学校の中に常駐させていただけると、こんなことができるようになります』とプレゼンさせていただいたところ、『うちの学校で始めてくれませんか』と手を挙げた学校があり、そこから『学校作業療法室モデル校』としてスタートしました。そこで活動に評価を得て各学校に広がっていきました。
色々と調整する中で困難だったのが『作業療法士は何をする人?』、『何ができる?』という疑問を解消することです。そこで学校との関わり始めとして行ったことは、『作業療法士はこういうことができます』ではなく、学校の先生の相談に対して『いかに喜んでもらえるか』、『悩みをいかに解決できるか』、『手軽にできるか』というニーズに応えることだけを中心に行っていきました。
そのニーズに応えていく中で『作業療法士は便利な人たちだな』と思ってもらえることで成果が広がっていき『学校に来てもいいよ』となったのが経緯です。キーパーソンになっているのが、校長先生と特別支援コーディネーターの先生たちでした。学校組織のトップである校長先生がいかにゴーサインを出してくれるか、それに対して先生たちが納得いただけるかが鍵でした。そこで作業療法士あくまで学校の先生たちのサポートであり、保護者との間に立つことや子どもの特性を捉えられることを校長先生とお話ししました。その結果、『うちの学校でやっていいよ』と言っていただけたのが大きなきっかけでした。
また飛騨市では『ふるさと納税』に強みがあります。この『ふるさと納税』を利用して作業療法の取り組みを応援できる仕組みがありますので、『ふるさと納税』で募った予算を『学校作業療法室』や他の活動に使えるようになっています。このように予算が確保されていますので、さまざまな活動につなげられるようになっています」
石戸:「現場からの評判が良く予算が付くに至った経緯は、素晴らしいです。現場のニーズにしっかりと答えていく中で、皆さんから評価されたのですね。作業療法士にはさまざまな仕事がある中で、子ども向けは特別なのかなとも思いますが、視聴者からも質問が届いています。『子ども向けの対応として専門の研修はされていますか。子どもへの対応に特化する困難などはありますか』というものです。学校に入ると普段の作業療法士としての仕事とは違うところもあるのではないかと思いますが、研修やノウハウの共有はどのようにされていますか」
奥津氏:「視聴されている方には、『そもそも作業療法士ってなんだろう』、『病院にいるリハビリをする人なのではないか』と思うかもしれません。手の怪我のリハビリをする人というイメージが強いかもしれませんが、リハビリというのは作業療法士のごく一部なのです。
作業療法士は、人が行う日々の活動を作業と呼んでいます。食事や睡眠、活動、仕事、子育て、恋愛など、それを全て作業療法士は作業と捉えています。この作業を本人がやりたいように、実現したいようにできるようにすることが私たちの仕事になります。普段の対応と違うことは、学校の中にはありません。なぜかと言うと、生活領域に対して直接アプローチするのが専門性です。難しいのは、病院や療育施設でアプローチすることです。療育だと生活の現場の病院や療育施設に子ども達が来ますが、子ども達が生活している学校、保育園、家庭に直接アプローチができるわけではなく間接的になり、上手く専門性が活かせません。むしろ、学校という生活の現場に直接、一緒に参加させていただくことで『現場で一体どういうことが起きているのか』、『そこにいる人たちがどういう思いを持ってどのように活動しているのか』を分析することで、初めて私たちの専門性を活かせるのです。そこで学校に入らせてもらうことは違和感がないどころか、最もやりやすいと言いますか、自分たちの技術が発揮できるので働きやすいというのが正直なところです。
こういったノウハウについては、NPO法人『はびりす』で『りすのがっこう』という活動を行っています。1年を通したオンラインの研修会ですが、実際に『学校作業療法室』で行っている『CO-OP approach』や自分研究という自分の特性を知るためのプログラムをオンラインでの研修を通して発信をしていますので、興味のある方はご覧ください」
石戸:「視聴者から『授業や学校全体に入り込んで実際に子どもたちの関わりを持ち始めるきっかけとしては、どのようなことを想定しているのでしょうか』という質問も届いています。授業の中で相談に来た子どもに対応するというよりは、授業や学校全体の取り組みの中へ日常的に入っていき、皆さんからお声がけをしていく形ですか。それともそういう時間があるのでしょうか。『CO-OP approach』を皆で自主的に学べるような時間があるのでしょうか」
奥津氏:「いくつかレイヤーに分かれており、1つは授業の時間をお借りして『CO-OP approach』のワークショップをしています。これは、子どもたちが自身で使えるようになったら良いですし、『作業療法士は何する人?』という質問に対する啓蒙的な意味も含めています。学校の中で設けているのは、昼休みの時間に相談したい子どもに対しては『作戦の相談にしにおいで』と部屋を用意しています。昼休みの時間に子どもたちから『友達と仲良くなりたいけどどうしたらいい』、『漢字を覚えるためにはどうしたらいい』といった相談があります。この前は、『おじいちゃんとの関係があまり良くないけど、どう関わったらいい』という相談がありました。さまざまな相談に作業療法士が対応しています。
このように、子ども直接からの相談もありますし、先生から直接相談を受けることもありますし、子どもから相談を受けた先生が『作業療法士に相談行くときっと良いアイデアをもらえるよ』と誘致してくれて、さまざまな角度、さまざまな入口で相談を受けています」
石戸:「アプローチ方法はそれぞれということですね。全方位に対応できる体制になっていると感じました。『参考にした海外の事例などがあれば教えていただけますか』という質問が届いています。
アメリカでは作業療法士が教育現場に入っているという話も聞いたことがありますし、『CO-OP approach』自体もカナダで生まれたものですよね。海外で作業療法士が学校と連携しているような事例はどのぐらいあるのか、何か参考にしたような海外事例がありましたら教えてください」
奥津氏:「実際にこの『学校作業療法室』のシステムを作るために2024年2月にアメリカへ行ってきましたが、すでに学校作業療法が50年前から行われていたのです。アメリカのすごいところは、作業療法士がいるだけでなくて、他にも言語聴覚士、理学療法士、臨床心理士、その他専門職というのが、各学校に1人常駐できるようにもシステムが組まれています。そのシステムを参考に『学校作業療法室』は作られています。
ただ、私たちの取り組みの強みとしては、アメリカですと各種専門職が入っていますが、制度の特徴として厳密に作業療法士がやれることが区切られています。
アメリカでは、主にライティング、書字に関すること、センサリー、感覚に関すること、あるいは、ADL、身の回りの持ち物管理、着替えや食事に関することのみに作業療法士が関われると区切られています。
そしてアメリカはIEPと言う個別支援計画が立っている子どもにだけ作業療法士が関わっていきますが、それだけでは実際に小学校回っている中で友達関係のことや感情のコントロールのことなど、対応しきれないケースがたくさんあります。その点、『学校作業療法室』は、関わる領域に区分は設けずに、あらゆる領域に対して関われるようにしているというのがアメリカとの違いとなってきます。
他にも学校の中に作業療法士が入っている国というのはありますが、データを色々と調べていくと、学校全体、診断や障がいの有無に関わらず、学校全体の児童・生徒に関わろうとしているモデルとしては、飛騨市で取り組んでいるモデルが多分、世界で初めてだと思われています」
石戸:「教育現場が医療や福祉と連携していくことは大事だと謳われながらも、なかなか実現ができてない側面もあるかと思いますが、奥津さんとしては今アメリカの話があったように、他の専門家との連携もされていらっしゃるのですか」
奥津氏:「学校作業療法士という名称なのですが、他にも臨床心理士、言語聴覚士が一緒に活動しています。ですので、『学校作業療法室』という名称ですが多職種連携で運営されています」
石戸:「『学校作業療法室』はあくまでも窓口であり、さまざまな専門家と連携されているのですね。視聴者からは複数の質問が届いています。1つは、『不登校の子どもにどのようなアプローチをしているのか』というものです。もう1つは、『自ら相談になかなか行けないような児童・生徒への対話をどのようにしているのか』というものです。元々のきっかけは不登校や行き渋りの子どもたちへの対応がスタートだったと思いますが、学校に入られた今、不登校の子どもたちにどのような対応していますか?また、行動として出ている子どもは気がつくことができますが、行動に出てこないけれどケアが必要な子どもに対しても、考えなければいけないと思います。そのような子どもたちの様子にどのように察知して対応されているのか。自分からなかなか学校に来ない、問題行動として出てるわけではないけれども、心で抱えてるものがある子どもたちに対してはどのように対処されているのか教えてください」
奥津氏:「不登校の子どもたちにどう対応してるのについては飛騨市の強みですが、『学校作業療法室』で主に関わるのはまず行き渋りの子どもたちです。行き渋りの子どもたちが相談に来たらすぐ保護者を呼んで、どのように生活をもう一度、形作るのか早急に作り直して、その後の経過を見て学校に戻ってくるってところまではサポートしています。逆に、現在完全不登校になっている子どもたちに対しては『ふらっと』の組織内に不登校の子どもたちが少しでも健康な生活を送れるように、体を整えることができるほか、筋力トレーニングできる筋トレマシーンのある部屋を紹介して来てもらうっていうような取り組みをしている『ふらっとラボ』があります。
このように『学校作業療法室』は初期である行き渋りの子どもたちに対応しつつ、完全に不登校になってしまった場合は、『ふらっと』という別の組織で対応するように階層を分けながらサポートをしています。
もう1つ質問である自分から発信できない子どもたちについて、どのように対応しているのかについては、全ての子どもたちに対応できているわけではないですが、さまざまな研修をしていく中で、『自分は悩んでいるのかもしれない』と悩みや困りごとに気づいていない子ども多いことがわかりました。そういった子どもたちに対して、『自分の考え方には癖があって、こういう考え方が強くなると毎日を明るく過ごすことや健康的に過ごすことが難しくなってしまうんだよ』という話を授業で行っています。
そこで『もしかしたら私、こういうことに悩んでいるかもしれない』と気づいた子どもたちから相談を受けるということもありますし、悩んでいる子どもたちにはどういった特徴があるのかを研修を通して先生たちにも伝えていってるので、そういった先生たちが『もしかしたらあの子、何か悩みがあるのかもしれない、相談を聞いてあげてくれませんか』と持ってきてくれることもあります。多分、全てはもちろんサポートできていませんが、気づいてもらう機会を増やすことはできていると思います」
石戸:「視聴者からは『素晴らしいアプローチ方法だと思う一方、全てが全てうまくいくケースだけではないのではないのでしょか』という質問も届いています。『今までで最もアプローチが難しかったなと思われたケースや、その際にどのように対応されたのか』についてもお話を伺いたいという質問もきていますがいかがでしょうか」
奥津氏:「実際問題、全てうまくいってるわけではありません。今すごく難しく感じていますが、ASD傾向の強い子どもたちです。アスペルガーと呼ばれるような区分の子どもたちは、周りはものすごく困っていても本人に困り感がない子どもたちに対して、どのようにサポートしたらよいのかということで、最近始めたのが自分研究という取り組みです。子ども達との対話を通して、子ども達自身がどのように周りから見られているのか、自分がどのように考えているのかを明らかにしていくアプローチです。
実際に取り組んでいく中で困難なケースに出会いますが、そのときには新しくシステムを組んでいく、新しい専門家を招いて『CO-OP approach』のように常にシステム自体をブラッシュアップするといったことで『学校作業療法室』を運営しています。
困難に至った子ども達に何が起きていたのかについて分かった場合、乳幼児期や幼児期から保護者にどうアプローチしていくのか、どう子どもたちを育んでいくと将来を予防できるのかというような予防的なアプローチにも取り組んでいますし、現在の子どもたちの成人期までを見通したサポートを飛騨市と連携しながら組んでいくといった取り組みもしています。今はまだ対応できていない子どもたちに向けたシステムを、どんどん直しながら、さらに良い対応ができるように進めています」
石戸:「視聴者からは実際に導入されての反応についての質問もきています。保護者や先生方の声もいくつかご紹介いただいていますが、『子どもたち、それから保護者、先生方、行政の反応について改めて教えてください』」
奥津氏:「行政の反応につきましては、今まで行政だと制度を作ることはできて条件を決めてそこに対して当てはめるということはできていましたが、より質的にフィッティングをさせていくのはどうしたらよいのかということですごく悩んでいます。質的に分析して、どういう制度をこういう段階で当てはめるとよいのか作業療法士がアイデアを出し助言をしてくれることに対して行政としては助かっている、質的な面が良くなったという感想を聞いています。
学校の先生からよくいただく感想は、子どもに対してどう関わったらよいのかということ、保護者と面談するとき特別支援学級に紹介しなければいけないことや子どもの生活に対して相談しなければいけないことに対するものです。どうしても1対1だと対立関係になりやすかったですが、間に作業療法士が入って3者の関係になることで、保護者とチーム的な連携が取りやすくなったという声も聞かれています。『作業療法士』対『先生と保護者』という構造になり先生も保護者側に立って相談ができるようになりますので、その後の保護者との関係性が築きやすくなったほか、話しやすくなって心理的な負担が軽くなったという感想はいただいています」
石戸:「非常に素晴らしいお話ですね。視聴者からは今後の展開についての質問も複数きています。1つは、全国に広げたいという希望があると思いますが、『その際にもっともハードルとなることは何か』というものです。もう1つが、今後のあるべき姿です。先生方や保護者の方々が自分で対応できるようになり質問が減ったというお話を踏まえての質問かと思いますが、『出口というのは、環境整備など学校による自立的な継続でしょうか、もしくは学校作業療法室はずっと継続していくことが重要なのでしょうか』というものです。イメージしている今後の理想的な形について教えてください」
奥津氏:「広げるにあたってどういうことがポイントになるか、どういうことが障壁になるかという質問ですが、おそらく想定されるのは3つです。1つはシンプルに予算です。2つめは、この活動ができる作業療法士をどう見つけるのかということ。3つめは、受け入れ側、学校の先生や教育委員会などの行政側がどのように受け入れるのか。広めていく上でこの3つが課題にはなると思います。
飛騨市の取り組みを他の市区町村の首長や教育長が視察して、『うちの市区町村でやってみよう』と持ち帰ってくださっています。他の組織のトップがやってみようと思っていただけたら障壁は突破しやすくなると思っています。
2つめの『学校作業療法室』の理想の形について、さまざまな子どもたちと関わっていく中で見えてきたこととして、いったん良くなったこともライフステージごとに新しい課題が生まれてくることがあります。小学校低学年、高学年、中学校に入ってからとライフステージごとに環境が変わって、新しい課題が出てきます。『学校作業療法室』は、障がいや課題がありながらも、生き生きと毎日を生きていけるようにするのが最終的なゴールなので、作業療法士の手を離れていくのが私たち専門家としては理想的な形になります。
『学校作業療法室』は『点で伴走する』イメージです。ずっと関わり続けるのではなく必要に応じて、今この時期で、この時期でと点で関わりながら、子どもたちや先生たちの生活をサポートしていくのが理想の形かなと思いながら日々活動しています」
石戸:「確かに、子どもたちからにしても、保護者や先生からにしても、うまくいっている時はよいけれども、ちょっとした時に相談できる先がある、居場所がある安心感も心理的にポジティブな影響につながると思いました。最後に一言、メッセージをお願いします」
奥津氏:「飛騨市で始まった学校作業療法室という取り組みは、まだまだ課題がたくさんあります。ただ、これからやっていきたいこととして、他の市区町や他の場所で『学校作業療法室』が始まっていき、さまざまな地域でチームを組みながら課題に対して取り組んでいけるような活動に広がっていくと良いなと思っております。今日のお話を聞いて興味を持っていただけた先生方や他の専門職の方がいらしたら、ぜひ一緒にこれから走っていっていただけたらとても嬉しく思います」
最後は石戸の「素晴らしい取り組みのお話をありがとうございました」という言葉でシンポジウムは幕を閉じた。