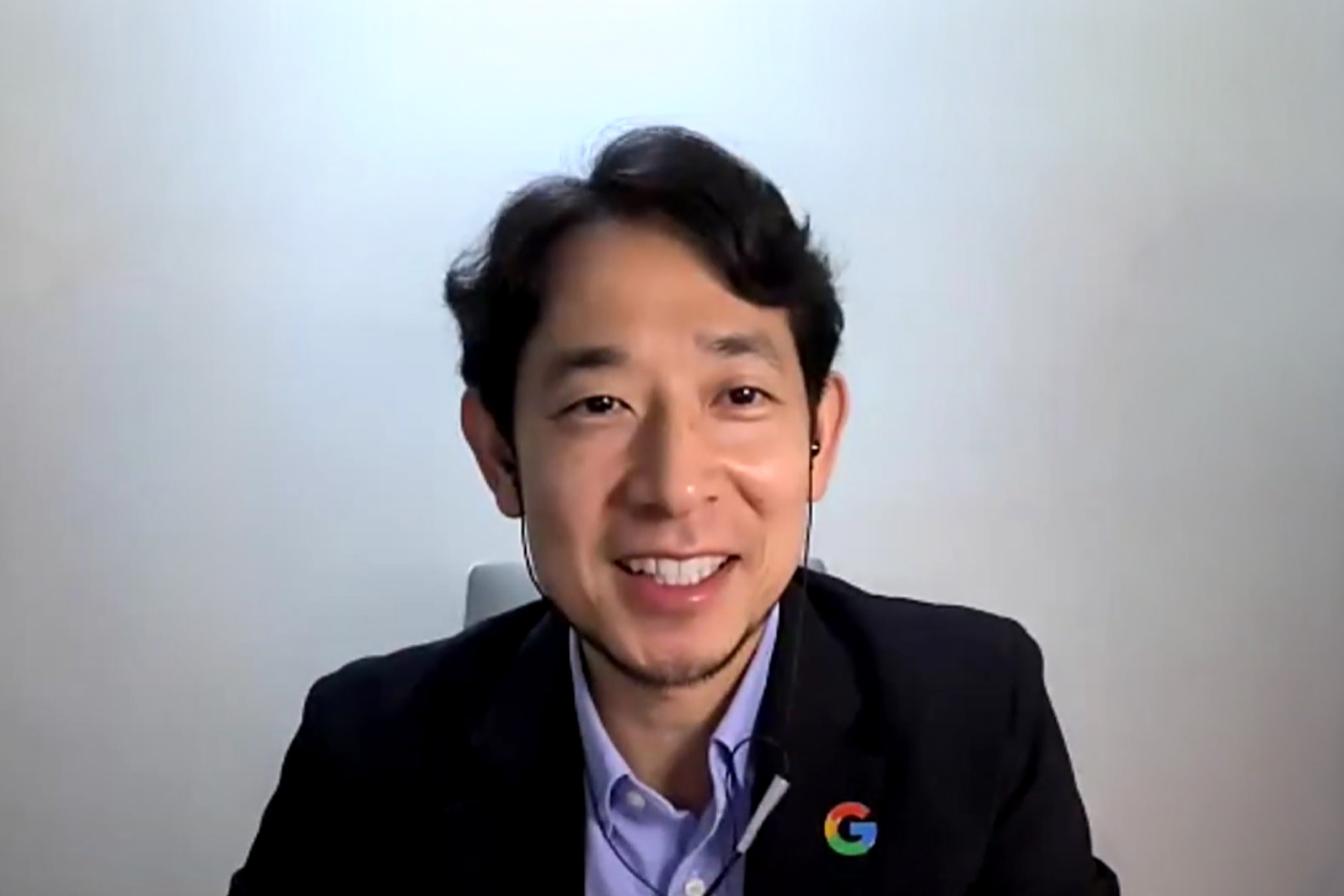概要
超教育協会は4月24日、香川高等専門学校 電子システム工学科教授/みらい技術共同教育センター副センター長の三﨑 幸典氏を招いて、「産学官連携からAI人材、学生起業家育成を目指す香川高等専門学校の取り組み」と題したオンラインシンポジウムを開催した。
シンポジウムの前半では、三﨑氏が産学官連携による学生起業家育成を目指す同校の取り組みについて講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その後半の模様を紹介する。
>> 前半のレポートはこちら
>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画
「産学官連携からAI人材、学生起業家育成を目指す香川高等専門学校の取り組み」
■日時:2024年4月24日(水) 12時~12時55分
■講演:三﨑 幸典氏
香川高等専門学校 電子システム工学科教授/
みらい技術共同教育センター 副センター長
■ファシリテーター:石戸 奈々子
超教育協会理事長
 ▲ 写真・ファシリテーターを務めた
▲ 写真・ファシリテーターを務めた
超教育協会理事長の石戸 奈々子
シンポジウムの後半では、超教育協会の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。
AIと「ものづくり」が香川高専の強み
石戸:「高専に対する期待やニーズが今まで以上に高まっていますが、社会からの要請や期待感の変化などを感じていらっしゃいますか」
三﨑氏:「それはものすごく大きいです。大きくなったので、逆に高専側がもっと頑張らないといけないと感じています。それだけの期待に応えることをやらないといけないという雰囲気です。産業界と繋がっている先生方もいますし、そういうことに後ろ向きの先生もたくさんいるわけですが、なるべく皆が同じ方向を向いてやって、香川高専全体としてうまくいくようなパターンを考えるのが私の仕事だと思っています」
石戸:「社会の高専に対する期待が変化するに従って、入学する子どもたちにも変化がありましたか」
三﨑氏:「何かやりたいと思って入学する学生が増えてきたような気がします。コロナが明けてから、自分でこういうことをやりたいと目的意識を持っている子どもたちが多いという気がします」
石戸:「目的意識を持って何か事を起こしたいと思う生徒も増えるというのは良いですね。地域連携でプロジェクトを起こしたり起業をしたりするとなると、これまでとは違うスキルが求められるのではないかと思います。カリキュラムをどのように変化させてきましたか」
三﨑氏:「ひとつは、学生がボランティアで地域の連携に関与することです。純粋なボランティアで参加することに対して、1年から5年までで1単位のボランティア単位を作りました。みらい技術共同教育センターで集計をして認定します。
一方、AIでエコシステムを作るには、AIの教育や、ビジネス教育やアントレプレナー教育は絶対必要だということで、AIのサマースクールを開講し、成功大学でAIの英語での講座をAI特化コースと称して入れました。今まではやりたくてもなかなか重い腰が上がらなかったのですが、ビジネス講座とアントレプレナー講座を昨年度の「高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業」の予算で開講し2024年3月に実施しました。ビジネス講座はちょっと変わっていて、香川銀行と連携しています。香川銀行にはビジネスゲームというのがあります。これは人生ゲームみたいなものなのですが、体験しながらビジネスを勉強できます。やっていて面白いし良く分かるということで、ビジネスゲームを用いたビジネス講座を30時間やっています。
アントレプレナー講座は、松尾研にお願いして昨年度にやってもらいました。今年度も継続して何とか頑張ってやろうと思っています。こうした形で学生はAIのスキルを身に付け、ビジネス教育、アントレプレナーの教育を受けて、自分が結局起業するか就職するか進学するかを決めたら良いかなと思っています」
石戸:「松尾先生のところとのアントレプレナー教育は具体的にどのような内容なのか非常に興味深いですね」
三﨑氏:「アントレプレナー教育は、学生は7、8人受講していますが、自分が今やっていることや、今、自分が社会で必要とされているものを見つけて、それがビジネスに成り立っていくかということを、モデルを立てながら、対象者は誰か、ペルソナは誰かということを含めてやっていて、最終的にビジネスモデルを書いてプレゼンできるくらいまでやります。だからけっこう面白いと思います」
石戸:「座学で聞くだけではなく、自分で具体的にビジネスプランを立てるところをサポートしてくれる授業ということなのですね」
三﨑氏:「そうですね。まずは講師の先生が教えてくれます。そのあと自分がチームで考えて、さまざまなプランを考えたり対象者を考えたり、それを訂正してどうするのか、これは本当にうまくいくのか、そのあとどのくらいのビジネス規模が取れるのか、そういうことを突き詰めて、最終的にビジネスとして大丈夫なのか結論を出します。それでうまくいかなければピボットを変えて別の事業に応用する、そういうことを学生はやっていました。だからけっこう面白かったと思います」
石戸:「それは学生にとってとても刺激的だろうと思います。もう一点、AI教育のところでされていることが非常に気になりますが、特にこの1年くらい生成AIの登場とともにAIを教育の中でどう使っていくかということと、AIを使いこなせるようにするためにどういう教育をするかという両面から、さまざまな学校で検討や導入をしていると思います。香川高専ではAI教育のカリキュラムをどのレベルのところまでやっていますか」
三﨑氏:「基本的には、プログラミングの授業としてAIの授業を取り入れている学科がほとんどです。取り入れられているのですが、それは最先端ではないので、それをベースにして、AIのサマースクールでブラッシュアップすることをやろうと思っています。
AIのサマースクールでは、松尾研の講師の先生が実際に研究していたり、多くの高専生の教育をしたりと、慣れている先生方がいますので、何が必要かということを30時間まとめてやってくれます。私は、1回目はわからなくてもあまり気にせずに、次の学校の授業である程度、勉強して、その次にまたもう一回サマースクールを受けるというのがよいかなと思っています。単位化していますが、単位は必要ないという学生も受講しています。受講する学生はたくさんいて、その中で勉強してまた次の年のAIサマースクールを受講するまでに何とかわかるようにしようみたいなパターンになると思います」
石戸:「複数の視聴者から次のような質問がきています。『起業家を育成したり技術者を育成するような大学などの教育機関というのもある中で、高専だからこその強み、高専ならではの強みをどのように捉えていらっしゃいますか』というものと、『これから先より一層強みとして発揮していくにはどういうことをされていくのですか』というものです。いかがでしょうか」
三﨑氏:「難しいのですが、松尾先生はAIと高専のものづくり、つまりプロダクトを作るという技術が融合するとこれほど強いものはないと言っています。三豊AI開発もそうです。電線点検ロボットで撮影した画像をAIで分析するというモデルですが、そういうのは大手の企業がなかなか真似できないです。また、今まで伸びてきた企業はソフト系やアプリ系ですね。そういうところは大手が入ってくるとなかなか立ち行かなくなるパターンが多いと思います。高専は、プロダクト、要するに『ものづくり』とAIを組み合わせられることが強みだと思いますが、ものをつくるところで時間とお金がものすごくかかって、そこを乗り越えるのは一番難しいかなと思います。でもそれを超えたモデルをどこかが生み出してひな形ができれば、どんどん加速されるのではないかと思っています。やっぱり、ひとつ成功モデルができるのが重要かなと思っています」
石戸:「このような質問もきています。『高専が抱えている課題やこれからの可能性についてお聞きしたい』ということです。社会全体で変化の時を迎える中で、高専としての課題意識や先の展望についていかがでしょうか」
三﨑氏:「やはり、高専は変わらないといけない時期に入っていると思います。スタートアップを含めて、もう少し社会や情勢を見て、各高専がそれぞれの特色を出して自分の強みを発揮していくということをやらなくてはならないと思います。私はたまたまAIと結びつき、松尾先生のところと起業するパターンを選びましたが、それがベストではないと思います。さまざまな取り組みを始めて、社会と繋がって地域社会に必要とされる高専を目指すべきと思っています。それを高専全体の方向性として皆をまとめていくというのも、大きな問題だと思います。校長先生がリーダーシップを発揮してどんどん進めていくのが良いでしょう。全体を動かすのは難しいですが、なるべくそれが主流になるようにはしたいです」
石戸:「全体を動かすのは難しいというお話がありましたが、高専の横の連携はあるのですか」
三﨑氏:「非公式な団体ですが、AIを活発にやっている高専を13高専くらい香川高専がまとめています。例えば、鳥羽商船高専が持っているAIが地域で使えるとなったら、鳥羽商船高専に提供して欲しいと言います。それでいかに早くよいものを作り上げるかという連携をやろうと思っています。たまたまですが、ずっと連携していた一関高専の荒木校長先生がこの4月に香川高専の校長になりました。連携していたので何をやりたいかわかっているので、方向性が定まってやっていけると思っています」
石戸:「香川高専のAIの導入や企業支援は、ほかの高専にも影響を与え始めているということですね」
三﨑氏:「そうですね。荒木校長もそう言ってました。頑張っているけれど、なかなか大変だよねと言われました」
石戸:「視聴者からこのような質問がきています。『三社も起業しているのは素晴らしいと思いますが、そういうことが周囲の生徒やほかの高専の生徒などに与える影響や、授業の態度に与える影響は何かありましたか』というものです」
三﨑氏:「学生はけっこう興味を持っていると思います。起業OBの会社説明会をしましたが、興味のある学生が多く集まりますね。それと、香川高専が起業を推進しているというので、今日も沼津高専のOBの宮田さんという方が講演に来てくれましたが、そういう起業OBの講演を学生にアナウンスした時に集まる学生の数が増えてきています。私がこうしろと言っても聞かないけれど、松尾先生や起業したOBが同じことを言ったら聞いてくれます。やっぱり外部からの刺激は大事です」
石戸:「よく聞かれるかと思いますが『AIがこれだけ普及し始めて教育の未来はどう変わるか、それに当たってどんな力が必要になってくると思うか』という質問が視聴者からきています。生成AIの登場によってどのように教育が変わるべきか、育むべき力はどう変わるべきかの議論が再燃していますが、香川高専として、それから高専全体としてそういった議論が改めて起きているのかお伺いしたいです。あわせて、AIを使うとプログラミングのやり方も変わりますし、ものづくりの仕方も変わってくると思いますが、その影響はあるのか、この2点についてお聞かせください」
三﨑氏:「岩本先生と研究をしていますが、2人ともAIの専門家ではないです。自分は超伝導のデバイスや超伝導の材料の専門でしたし、岩本先生も半導体のSiCとパワーデバイスの研究者でした。そういったAIの専門家でない人がAIに興味を持って研究することができる時代に入ってきたと思います。私は岩本先生と連携してAIとハードウェアを結びつける研究をやっていますが、そういうパターンがどんどん出てくるのかなと思います。
AIの教育も、専門家が一からコツコツ教えるという従来型の日本の教え方ではなく、まずやってみて、ソフトを動かしてみて、なんか困りごとがあるけれどこうしてみたらどうかといった感じのプログラミングの授業がどんどん出てくる可能性があると思います。そうやって使えるとなれば、自分の研究や開発で使って、研究室に広がっていくのではないかと思っています。『使えるものは使え』という意識でやっていくという教育方針であれば、そういう方向性になるかもしれません。まずはできるところから進み、深みに入って最終的には理論を含めて全部を勉強してしまうということになれば、とても強いのではないかと思っています」
石戸:「次のような質問もきています。『地方では普通高校の改革が遅れていて、受験者数の低下が問題になっています。各学校、学科の垣根を超える高等学校改革推進事業などの対象に高専が入っていないようですが、普通高校との単位互換などの交流ができると良いと思います。いかがでしょうか』というものです。いかがでしょうか」
三﨑氏:「普通科だと主要5科目になると思います。それと連携できるかというと難しいかもしれないですが、普通科の高校から4年生に編入することは香川高専では可能です。3年までは授業が必修科目になっていて、それを単位互換するという考え方はないので、選択科目になると例えば大学の単位を取りましょうみたいな感覚にはなるのですが、そこが問題かもしれません。そんなことは考えたことがなかったので、うまくやればいけるかもしれないとは思います」
石戸:「地域や企業との連携を盛んにされているとのことですが、『企業に与えた影響はどのようなことがあったか』という質問が視聴者からきています。あわせて地域に与えた影響、高専生が地域に出ていくことによって、企業側がこう変わっていたという相乗効果の具体的な良い事例がありましたら、教えてください」
三﨑氏:「学生が地域に出ていくことによって、地域が必要としているということを学生が認識できます。私は吹奏楽もやっていて、吹奏楽で一番学生のモチベーションを上げる方法は、地域に出ていって演奏することです。例えば小学校や幼稚園で演奏するとみんな喜んでくれますよね。自分の演奏を喜んでくれたと肌で感じるのがモチベーションアップにつながります。それと同じで、学生が地域に出ていって貢献したことについて、『すごいね』と言ってもらえると、学生のモチベーションは当然、上がります。それが、自分は求められている人材なんだなという意識になると思います。それがだんだん広がっていくと、地域の方からこういうのできませんか、ああいうのできませんかと言ってくれるようになるし、会社でもこんな技術ないですかという問い合わせに繋がってくると思います。それが発展していくと多様なシーズが生み出せるようになって、最終的にはそのシーズを核にして、AIと組み合わせて新しい会社を起業するとか、そういうところまで繋がればよいと思っています。だんだん地域に必要とされる高専に近づいているかなと思っています」
石戸:「最後に、視聴者からきている質問を取り上げたいと思います。『シリコンバレーに勝てるのは高専生だと言う方がいらっしゃいますが、今後、世界で日本が活躍できると思われる分野や、そのために必要なことは何だと思いますか』というものです」
三﨑氏:「シリコンバレーみたいに、ひとつの会社が立ち上がって投資を受けて技術者を集めて、失敗すれば解散みたいなことは日本では無理だと思います。ただ、香川高専から起業した会社が10社15社できれば、例えば1社が投資を受けて何か作ろうとなった時、それぞれの会社が集まって協力して、その1社のプロダクトを作り上げて製品化するという形が理想的だと思っています。その中心に香川高専がいるべきだと思っているのですが、それ以上のことは私には答えられません」
最後は石戸の「みんなで連携して世界に出ていこうということだと思いますし、共創のプラットフォーム、共創のエコシステムを作るというのが香川高専の一番の肝と感じました」という言葉でシンポジウムは幕を閉じた。