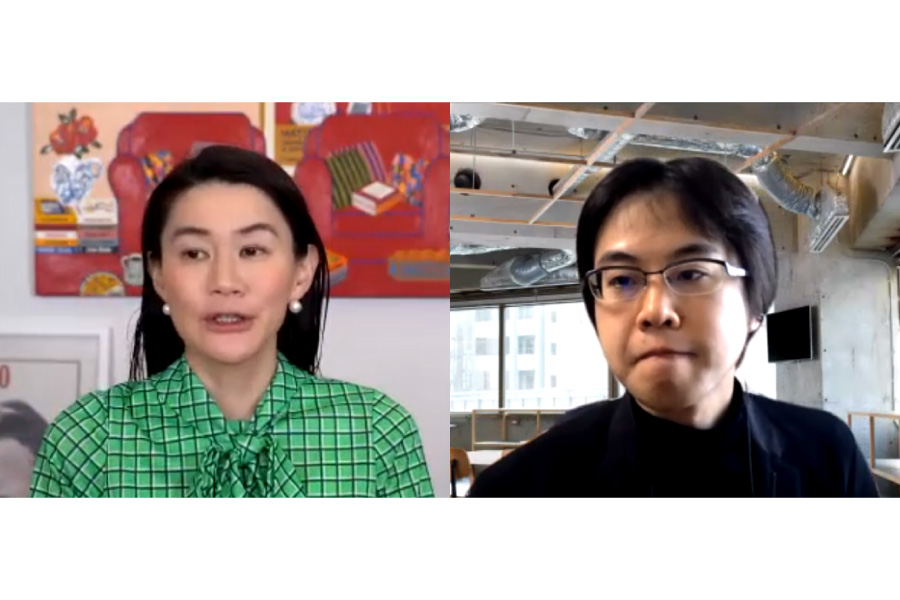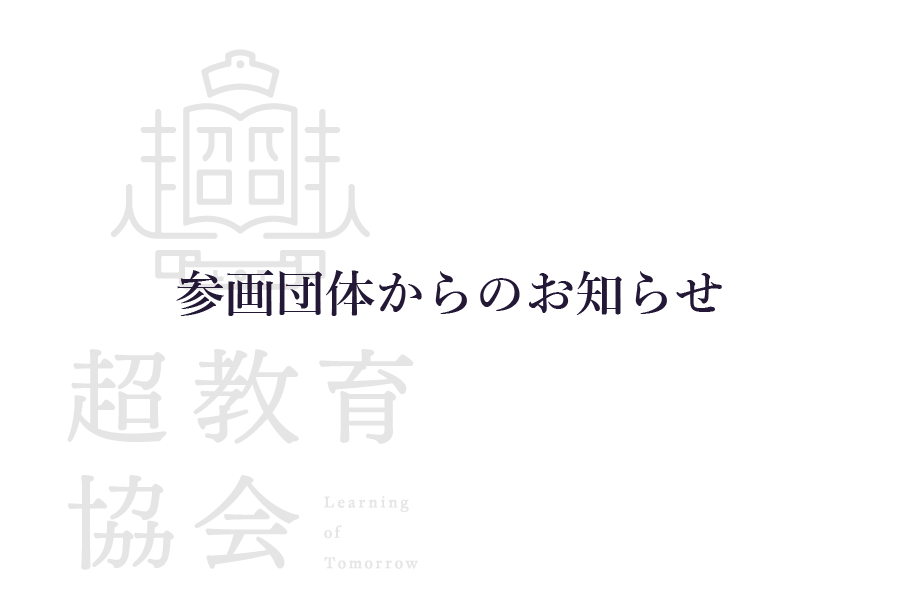概要
超教育協会は2021年3月24日、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授の南澤孝太氏を招いて、「触覚から人の可能性を拡張する~『Haptics』で実現できること」と題したオンラインシンポジウムを開催した。
シンポジウムの前半では、南澤氏が、「触覚」を扱うテクノロジーとその実践活動に関するプレゼンテーションを行い、後半では、超教育協会理事長の石戸奈々子をファシリテーターに参加者を交えての質疑応答を実施した。その後半の模様を紹介する。
>> 前半のレポートはこちら
>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画
「触覚から人の可能性を拡張する
~『Haptics』で実現できること」
■日時:2021年3月24日(水)12時~12時55分
■講演:南澤孝太氏
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授
■ファシリテーター:石戸奈々子
超教育協会理事長

▲ 写真・ファシリテーターを務めた
超教育協会理事長の石戸奈々子
シンポジウムの後半では、ファシリテーターの石戸が参加者から寄せられた質問を紹介し、南澤氏が回答する質疑応答が行われた。
「触覚」を教育に活用することに高い関心が寄せられた
石戸:「最初の質問は、『触覚には、味覚の甘い・辛い・しょっぱいといったような区分はありますか。また、再現しやすい触覚、再現しにくい触覚はありますか』というものです。合わせて私から追加で『触覚の感じ方は人それぞれで、感覚過敏の人も感じにくい人もいるが、触覚を再現するときにそういう感じ方の差異をどう認識されているか、また、感じ方の差異を伝えるために役立つ技術はあるか』についてもお伺いできればと思います」
南澤氏:「触覚の前に、まず視覚について説明します。視覚は、映像をRGBすなわち赤・緑・青という色の三原色に分解し、そこに『明るさ』という概念をプラスされることで映像を伝えています。これがコンピューター上で再現できるのは、人間の目の中ある、赤を見る細胞、緑を見る細胞、青を見る細胞の仕組みをテクノロジー的に真似ているからです。
私たちは、この概念を触覚にも応用しようとしています。触覚は基本的に、触った時に感じる圧力、ザラザラとかサラサラといった振動、それに温度で構成されていて、これを『触覚の三原色』と呼んでいます。何かに触れたときの感覚は、基本的にこの3つの組み合わせで伝達できることはすでに判明していて、これが『触原色原理』、いわば触覚をフルカラーにするという概念です。
ただ触覚が視覚と比べて難しいのは、私たちが何かに触れる時、常にアクティブに動いていて、止まったまま触れている状態にはほとんど意味がないということです。例えば、誰かの頬を指でつつくと相手の頬も自分の指も凹むように、触る時に相手も自分も変化します。また、同じ頬に触るにしても、軽く撫でられるのと、パシンと叩かれるのでは意味も感覚も経験も変わってきます。単に肌の感触を再現すればいいのではなく、そこに込められた意味や意図のようなものまで再現しないと、情報としては正しいけれども、経験としては違うということになってしまう、ここが触覚の面白くかつ難しいポイントです。
このような、視覚と比べてダイナミックな変化に加えてもう一つ、触覚は体を使って触れるため、その体の違いが出てきます。例えば、若い人の指と高齢者の指では、皮膚の固さが全然違いますので触覚も変わってきます。このあたりは、最近共同研究を行っている名古屋工業大学の田中由浩先生が詳しく、高齢者の指先の弾性などを調べて自分の指が、老化したときの感覚を再現されたりしているのですが、このような身体的な違いも重要なファクターになってきています。
視覚の場合、視力検査で視力・色覚・乱視・弱視などを調べて、ある程度矯正していく仕組みがあります。もし『触力検査』のようなものがあれば、触覚の個人差がもう少しクリアになり、研究が進むのかも知れません」
石戸:「ここのところVR関連のオンラインシンポが続いていたこともあって、発達障害の方の感覚の差異をどう共有するか、というところにVRが有効ではないかと思っていたのですが、触覚も同様ですね。個人差のある感覚をどう共有するかという観点で非常に興味深いと思っています。
次に『触覚×教育』という観点で『触覚は特別支援教育との親和性が非常に高いように思われますが、特別支援学校での触覚を使った教育支援の取り組みに、どういうものがあるのか』という質問です」
南澤氏:「今、私たちが進めている事例として、お台場の青海特別支援学校と一緒に行っている取り組みがあります。特別支援学校の子供は、もともと外出に対する障壁が大きいのですが、それがコロナ禍で一層困難になって、いろいろな体験ができなくなってしまっています。そこで、触覚を使った疑似体験で校外のさまざまな感覚を届けようという授業を実施しています。その結果、言葉だけではよく理解できない子供たちも、そこに触覚が加わることで『何が起きたんだ、何が来たんだ』と興味や関心を高めてくれることがまずわかりました。
そこで、次のステップとして始めたのが『触覚で感情を届ける』というプロジェクトです。特別支援学校に通う子、特に自閉症の子供は言葉で感情を伝えるのが苦手で、体を使った感情表現を多用します。この『体で表現した感情』をそのまま触覚的に届けられれば、より相手に伝わりやすく、しかも、自分でその感覚を振り返るようになれるかも知れません。
ということで、日本科学未来館、青海特別支援学校と共同で『感情を触覚にする』共同プロジェクトが始動し、昨年12月の障害者週間には、コロナ禍ですが日本科学未来館で発表を行いました。視覚と聴覚に頼る従来型のメディアで伝えられなかったことも触覚を含む体験レベルでは意外と伝えられるケースが多いのではないかと考えています」
石戸:「講演に出てきたバスケットボールの事例でも、どういう形で『体験が伝わった』という評価軸を設定しているのか気になっていたのですが、そのあたりはどう計測しているのですか」
南澤氏:「そこは難しいところで、『どこに着目するか』で評価がけっこう変わってしまいます。従来の触覚の研究では、本物と間違うような高レベルの情報を伝え、正しく判別できる『精密さ』が重視されてきました。ただ、経験には個人差があって本物とのズレも人それぞれですし、私たちが昔の経験を振り返った時も、ディテールは残っていないでしょう。私としては、ディテールよりも記憶や体験に残る部分が、きちんと伝わればいいのではないか、と考えています。例えば、幼稚園の時にブランコで遊んだときのヒューンという感覚って何となく残っていませんか。
講演で紹介した、紙コップでビー玉を回す仕組みも、そういう考え方で作っています。空のコップに伝えているのは一点の振動だけで、ビー玉の細かい動きなどは全く伝えていないのですが、空のコップを持った人は誰もが『ビー玉が回っている』と言います。これは、その人の経験の中に『物が回ったらこういう振動が来る』という記憶があり、そこをきちんと刺せれば、記憶と触覚の刺激がマッチングして、頭の中に経験が立ち上がるのです。
バスケットボールの観戦の場合にもそういった瞬間がありますが、ドリブルとかよりも選手がちょっとコケそうになった時とか、そういった『微妙な変化』が来た瞬間によりリアリティが高まります。ここは言葉で説明するのが難しいのですが、『情報として意味のなさそうな部分』の方が、リアリティや存在感、自分がやっているという実感などの記録に残りやすく、そこをいかにサイエンスとして言語化し、伝えていけるかが勝負だと思っています」
石戸:「情報を伝えるというより『体験』を伝えるというのは面白いですね。講演では特別支援学級での取り組みについてお話しいただきましたが、『教育×触覚』という観点で、ほかにどういう研究が進んでいるのか、もしくはまだ研究はそれほど進んでないのかについて、もう少し伺いたいと思います。VRの場合、以前からの『臨場感ある体験』に加えて、『VRを使った高速学習』や『他者視点によるソーシャルスキルトレーニング』といった、従来の教育では難しい学習の実現に可能性を感じていて、そこに教育的効果があるというエビデンスも明らかになりつつあります。
一方で触覚に関しては、教育の中でどういう使い方が想定されているのか、現時点で具体的なエビデンスが出ているものがあれば教えていただけますか」
南澤氏:「わかりやすい例では『繰り返し学習』があります。卓球のコーチングに触角を使ってみたことがありますが、スポーツのコーチングは、コーチだけが知っている正解=コツを得るために、生徒はとにかく繰り返しながらコツを学んでいきます。それなら最初からコツを伝えてしまえばどうか。例えば『今、芯に当たった』とか『今、うまくいった』という経験を先に知った上で練習すると、すごく効率が上がるだろうという話をしていました。これはまだエビデンスがあるわけではありませんが、少なくともコーチの人たちと議論やトライアルを重ねた中では、感覚レベルでの正解を先に与えることは、高速学習に効果があるという意見が大勢で、特にスポーツのように言語化できない、体の運動機能をどうトレーニングするかというところでは大きな意味があると考えています。
もう一つ、モチベーション系にも効果が期待できます。高齢者の方のリハビリは、『今日は200歩歩きましょう』だけでは当人のやる気を引き出せず、効果が上がりません。そこで、『ここはおじいちゃんの好きな山ですよ、山をザクザク登って風景を楽しみましょう』となると、皆さんポジティブになって体を動かすようになります。こういうモチベーションを誘発できるところも触覚の重要なファクターです」
石戸:「人間の体験を伝送するのに、視覚・聴覚・触覚といったいわゆる五感は各々どのくらいの割合で認知されているのですか」
南澤氏:「よく『人間は視覚が7~8割』と言われ、それはある意味正しいと思いますが、触覚は視覚よりプリミティブなところで重要な役割を果たしていると思います。『情報を伝送する』ところでの役割は大きくありませんが、『自分が感じた』とか『自分がやった』という主体感、あるいは実感を伝えるところには、大きく寄与しているのです。
博物館のコンテンツを『触覚あり』と『触覚なし』のグループに分けて体験させ、ひと月後に聞き取りをした実験でも、『触覚あり』のほうがよく記憶に残っているという結果が出ています。教育現場でも同じだと思いますが、ただ聞いているだけだと頭の中でどんどんスルーされてしまうところが、自分が主体となって何かを行うと、その経験がファクターになって記憶に残るということが大きいのだと思います。そういう意味で、情報量という観点で測ると役割は小さくなってしまいますが、記憶のプライオリティや重み付けのところではすごく重要な要素になっていると思います」
石戸:「ありがとうございます。次は非常に興味深い質問で『痛みを再現することはできますか』というものです。児童や生徒の体の異変について、どの程度深刻なのかを先生が察知するところに使えるかなと思いますが、いかがでしょうか」
南澤氏:「できるかできないかで言えばできます。一昨年頃ですが、IVRC(国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト)に出場していた学生の作品で『生理痛』の体験を作ったグループがありました。
もちろん女子学生もメンバーの中にいて、自分たちの痛みと突き合わせながらトライアルを重ねて再現したのだと思いますが、実感としては『めちゃくちゃくる』感じで、ちゃんと内臓感覚を刺激するようになっていて体の奥の方から痛かったですね。
このように痛みを再現すること自体はできるので、生理痛のような男女の差を実感するとか、最近だとDVを行う人に対して相手の痛みを理解させるといったところでアプリケーションとして使われ始めている事例もあります。ただ、『本当に痛いコンテンツ』では使いどころも限られてきてしまいますので、必ずしも忠実に再現しないほうがいい場合もあると思います」
石戸:「ありがとうございます。教育現場でどういうシーンに触覚を使うと『伝えること』の価値がより理解されやすいのかを先ほどから考えていまして、『子供達の身体の様子を伝えられる』可能性があるのは非常に興味深いと思いました。
最後になりますが、『教育への活用』という観点でメッセージをいただけますか」
南澤氏:「今回は『触覚』をテーマにお話しさせていただきましたが、あまり狭くとらえず『身体感覚』としていろいろな現場で扱っていけばいいと思いますし、それがひいては、私たちがこれまでどういう経験をしてきたのかという話につながると思います。私たちは体を動かして周囲の人や物と触れ合い、さまざまな経験を重ねて自分自身を構築してきたわけですが、テクノロジーの分野ではそういうところが意外と忘れられて、映像や文字だけの実感を伴わない形で情報を伝えようとしがちです。
そこでもう一度、子供の頃からやってきた経験や体験に意識を向け直していただければ、新しい可能性が広がってくると思います。技術的にもそういうところが追いついてきていて、皆様をお手伝いできることもあると思いますので、何かありましたら宜しくお願い致します」
最後は、石戸の「本日の講演を通じて、『体験とは何か』を改めて考えさせられました。子供たちが一つの事象を通じて体験していることを、もう一回細分化して見直すきっかけになると思いました。『触覚』が教育現場でより活用されても良いタイミングに来ているとも思っていますので、その動きをより加速できるようにご一緒させていただければ嬉しいです」という言葉でシンポジウムは幕を閉じた。