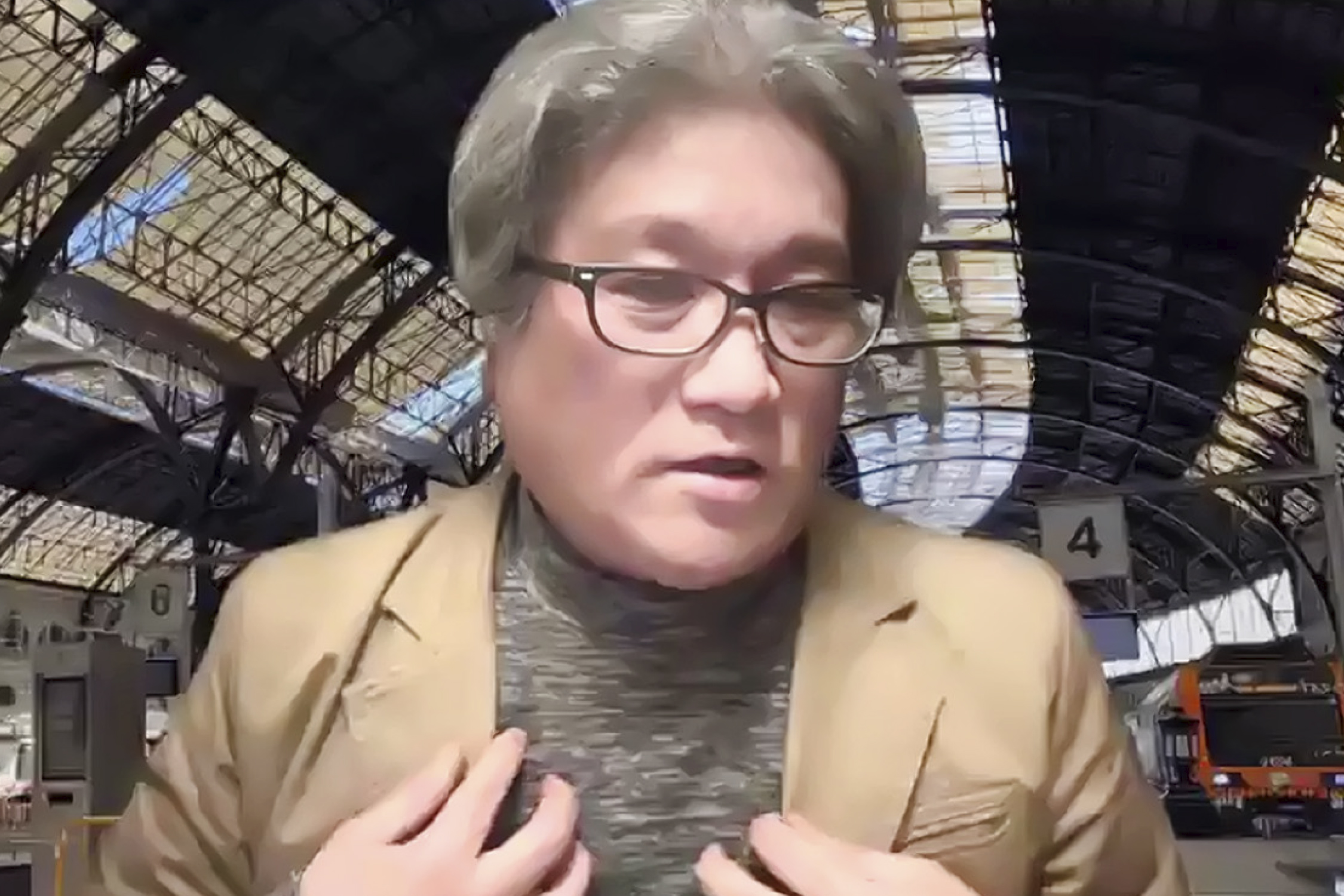概要
超教育協会は2025年9月10日、東京書籍株式会社 みらいBizスタジオ第一室 室長の東井 尊氏を招いて、「AIとの対話で、学びを深める『教科書AIワカル』」と題したオンラインシンポジウムを開催した。
シンポジウムの前半では、東井氏が「教科書AIワカル」の開発経緯やサービスの特徴、今後の展望などについて講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その後半の模様を紹介する。
>> 前半のレポートはこちら
「AIとの対話で、学びを深める『教科書AIワカル』」
■日時:2025年9月10日(水) 12時~12時55分
■講演:東井 尊氏
東京書籍株式会社 みらいBizスタジオ第一室 室長
■ファシリテーター:石戸 奈々子
超教育協会理事長
 ▲ 写真・ファシリテーターを務めた
▲ 写真・ファシリテーターを務めた
超教育協会理事長の石戸 奈々子
シンポジウムの後半では、超教育協会の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。
定量的な学習効果、英語以外への展開 現状の課題などに質問が集中
石戸:「子どもたちの『定量的な学習効果』、子どもたちの『学び方の変化』、先生の視点から見た『先生の役割のこれから』各々について、実際の授業現場でこれまで見られた変化や、それを踏まえた今後の方向性についても、子どもと先生の両方の視点からお聞かせください」
東井氏:「私たちもまだ模索の段階ですが、約1カ月半の実証実験を通して見えてきたことがあります。学習効果については、AIを使って約1カ月半での実証は難しいところです。ただ、ある先生は『生成AIとのやりとりを繰り返すことにより、これまでは英作文を一つしか作れなかった生徒が二つ、三つと書けるようになった』という声をいただきました。こうした具体的な変化が見られる学校もあります。生成AIがそばにあることで、いつでも手軽にわからないことを聞けるようになり、学習効果向上にもつながっていると考えられます。分からないことをそのままにせず解決できる点は、先生にとっても大きな利点です。長期的には、こうした積み重ねが確かな効果につながると感じています。
学び方の変化においても、疑問に思うことを解決してくれる存在が自分の学習端末の中に存在していることで、分からないことを分からないままにせず自分で解決できます。学び方という意味でも大きく変わりつつあると感じています。
実証では先生方の授業の構築が素晴らしいと思いながら拝見していましたが、こういうツールがあることで授業の構成も少し変わってきているのではないかと思います。これまでは一斉指導が中心でしたが、一斉指導50分の中で10~15分でも、個別に自分のやり方で学ぶ時間をきっちり設けることで、一人ひとりの学習者中心の学び方が実現されていると感じました。
先生方の役割については、まさにこれからの検討課題だと思います。先生方がどのような役割を果たしていくのか、変わっていく部分もあるでしょうし、変わらない部分もあるとは思っています。ただ少なくとも授業を見ている中では、先生がいらなくなるという乱暴な議論には全くならないと思っています。先生とAIが共存しながら、より良い利用が実現していくと考えており、その中で先生の役割が若干変わっていくと思っています。そこに関しては今日の時点でまだ明確にこうなるとは言えないですが、実証で使っている先生方と一緒に議論しながら、方向性だけでも今年度で見えてくれば良いなと考えています」
石戸:「今回のプロダクトは教科書準拠が特徴ということでした。一方で、子どもたちがAIに深掘りの質問をしていけば、当然、教科書に書かれていない内容にも踏み込むはずです。教科書準拠とは、どのような意味で使われているのか。また、子どもたちが探究を深めて、世の中の網羅的なことに対して質問していった際に、このサービスはどう対応しているのかについて教えてください」
東井氏:「教科書準拠という言葉は、使い方として難しいですが、我々のサービスは、教科書に書かれた内容しか回答しないというものではありません。あくまでも教科書の内容を参照しながら回答を生成できるツールになっています。つまり、教科書を入り口にして、もっとこの内容が知りたいという場合には、生成AIの能力を使って、さまざまなコンテンツを生成していきます。
特に中学生段階では、教科書に沿って回答した方が理解しやすい場合もあるため、教科書にのっとった回答をしていく方が望ましいと考えています。そういった内容については、教科書に記載している内容から回答を生成します。それ以外のものに関しては発展的に生成AIが持っている力で回答していくというサービスです。準拠といっても教科書のことしか答えてくれないという意味ではありません」
石戸:「視聴者からは『家庭では子どもが既にGeminiやChatGPTを使って勉強しています。教科書の内容をコピペして質問することもありますが、それとの差分があれば知りたい』という質問が届いています。汎用型の生成AIとの違いはどこにあるのでしょうか」
東井氏:「教科書の内容をコピーしてChatGPTやGeminiに入力して活用するのも生成AIの一つの活用法です。我々のプロダクトには、学習者がわざわざコピーして入力しなくても、教科書の内容はあらかじめ組み込まれています。教科書のページやユニット名を指定することで関連内容をすぐに呼び出せるようになっているところが違います。
また『これがわからないので教えてください』、『これの類題を教えてください』といった使い方は、たしかにChatGPTなどでもできるかと思います。しかし、『授業モード』については、『どういう手順で学習を進めていくと身につけて欲しい知識を学べるのか』といった学習ノウハウが組み込まれています。これは、当社がこれまでの知見の中で積み上げてきたものです。ここについては、なかなか汎用型の生成AIでは代替できないと考えています。あくまでも教科書をしっかり学習していくことに関しては、汎用型の生成AIとは異なる利点が見出せると思います」
石戸:「視聴者から『LLMの年齢制限にはどのように対応しているのか』という質問です。『OpenAIのAPI利用は18歳未満の保護者の同意が求められていますが、その点はどのように検証しているのか教えて欲しい』という内容です。いかがでしょうか」
東井氏:「我々のアプリケーションでも、年齢制限は設けています。LLMが設けている年齢基準も遵守しつつ、利用する前に年齢確認をするように設定しています。確実にブロックできるわけではありませんが、小学生以下のお子さんの使用は推奨していませんという制限を設けています」
石戸:「AIが広く普及してきた今、そもそも子どもたちは何を学ぶべきかという学びの内容自体を見直す時期にあると感じます。教科書会社としては自らの役割をどのように定義されているのか、これだけ世界中の知識にアクセスできるときに、教科書のあり方はどうあるべきなのかに関しても、ご意見を伺えればと思います」
東井氏:「ものすごく問いが大きくなってしまうので、東京書籍のDX部門の担当者としての立場でお答えします。確かにいただいた質問はもっともだと思います。一方で何を学べばよいのかについて、どなたが指針を出すのか、それが難しくなってきています。何を学べばよいのか、しかも、どの手順で学べばよいのかは、人によってバラバラになりつつあるような状況だと思います。そうした中で、教科書という基盤となるような教材があるからこそ、教育の質が担保されている面があります。形は変わるかもしれませんが、学ぶ内容や順序、系統、体系、正当性が担保されたものがなくなることはないとは思っています。ただ、それがある上で一人一人がどうやって身に付けていくか、学び方や手法は変わっていくかと思います」
石戸:「技術の進歩に伴い、教育現場にも変化が求められています。単に既存の教育システムに技術を取り入れるだけではなく、教育そのものがどのように変わっていくのか、そしてその変化を支えるために技術をどう活かしていくのか。そこにこそ、これからの教育の本質的な課題があると感じています。本日ご紹介いただいたサービスは、その問いを深く考えるための大きなきっかけとなりました。
視聴者から『学習意欲が高く言語化が得意な子どもの学習はAIでどんどん進んでいきそうなイメージを持ちましたが、一方で、あまり学習意欲が高くなく言語化が得意でない子どもに関しては、一人で進めていくイメージが持てません』というご意見です。それに対して、このプロダクトで動機づけをしていくのか、もしくは、そこの部分は先生の役割なのか、現時点で見えてきていることがありましたら、教えてください」
東井氏:「1つのサービスだけでどこまでできるのかは、なかなか難しいところではあります。学習意欲が低い理由は、いくつかあると思います。そもそも分からなかったから意欲がなくなったという子どもたちに対しては、プロダクトはすぐに何らかの反応が返ってくるツールとなります。分からないことがその場で分かるようになり、自分の疑問がその場ですぐ解決できるということが、少しずつ学習力の向上にもつながっていくというのは、先生方がおっしゃっていたことでもあります。
このことから、一定程度の影響はあると思っています。ただ、そもそも意欲がない子どもたちに対しては、先生方、つまり人のサポートが大切で、それが先生方の役割でもあると思います。指導に関わっている先生方が学習者に向き合う時間が増えていくにつれ、プロダクトで『ツールでできる部分』と『人でできる部分』が役割として、もう少しわかるようになると考えています」
石戸:「今回は、生成AIを家庭教師のような個別支援の位置づけで活用されているとのことですが、視聴者からは『個別学習だけではなく、クラス全体や少人数での共同学習に発展させていくことも考えていらっしゃるのでしょうか』という質問も寄せれています。クラス単位での活用、つまり学び合いを支援する新たなツールとしての生成AIの導入については、どのようにお考えでしょうか」
東井氏:「今のところ、このプロダクトを共同学習に使えるように機能拡張をすることまでは考えていませんでした。ただ当社として、さまざまな学習支援の中で生成AIをどう活用していくのかについては、今後も検討していくことだとは思います。このプロダクトということではなく、さまざまな支援で生成AIを活用できるようなサービスは、引き続き検討していきたいと思います」
石戸:「私自身も、生成AIは自分の思考を深め、広げてくれる非常に有効なツールだと感じています。一方で、視聴者からは『宿題の答えをAIに聞いて、そのまま書いてしまうのではないか』といった懸念の声も多く寄せられています。この点について、どのような工夫をされているのでしょうか。
私個人としては、『答えを求める宿題』から『考える力を育む課題』へと転換していく必要があるのではないかと感じています。とはいえ、現場の先生方の中には、実際の対応に悩まれている方も多いのではないかと思います。そうした課題に対して、どのような働きかけや仕組みづくりをされているのか、またサービスとしてどのような工夫をされているのかをお聞かせください」
東井氏:「非常によくある質問です。最近まで『そうですね』としか答えられなかったですが、プロダクトとしてはシンプルに『答えを教えて』という質問に対しては、極力、一緒に考えることを促すようなプロンプトをあらかじめ入れています。つまり、そう簡単に答えを教えないような設計にはしています。先生方がおっしゃっていたことですが、生成AIの初回の使い方として、『わからないから答えを教えて』から入るケースは正直、多いとのことです。ただ、子どもたちを見ていると、そこで止まることもあまりないと先生方はおっしゃっていました。
我々のプロダクトでは、答えを聞いて教えてくれた後に、例えば、『同じ例題に取り組んでみようか』、『どこがわからなかったのか。もうちょっと詳しく教えようか』というような、次の問いを促すような回答を生成するように我々のプロダクトはしています。
入り口は答えを聞いただけかもしれませんが、さらに次の問いが生まれる、次の問いを促すような仕掛けをしていますので、答えを聞くところから、さらに考えを深めていくような使い方もできます。まずは答えを聞くところから始めていきながら、実はもっともっと、さまざまことに付き合ってくれるパートナーなのだというところに気がつく、そんなことが実際に使用していただいて見えてきています」
石戸:「これまでも、生成AIに限らず、新しい技術が登場するたびに、教育への活用の是非が繰り返し議論されてきました。現在、生成AIについては、高等教育では、議論もある程度落ち着き、活用を前提とする動きが広がりつつあります。しかし一方で、初等・中等教育におけるAIの活用のあり方については、いまなお慎重な議論が続いていると感じます。実際にこうしたサービスを開発し、現場で運用されてきたご経験から、初等・中等教育におけるAI利用のあり方をどのようにお考えでしょうか」
東井氏:「AIは使い方も含めて、まだまだ検討すべきところがあると思っています。ただ、実際に先生とお話をしていると、使っていくことに対するハードルは思った程には高くないと感じています。むしろ、教育の質が上がっていくという声の方が多いと思います。こういう良いツールを使って初等・中等教育にある、さまざまな教育課題を一緒に解決をしていきたいという思いの方が強いので、課題はありつつも実践を積み重ねながら、良い事例が入ってくれば啓蒙していきますし、それが結果的に質の向上につながっていくと考えています」
石戸:「デジタル化のときに比べると、AIは効果が可視化されやすい分、比較的受け入れられやすいという印象を受けました。
視聴者の皆さまからも多くのご質問をいただいており、特に多かったのは、『他の教科への展開はあるのか』、『現時点での課題は何か』といった点でした。最後に、現在感じていらっしゃる課題や今後の改善の方向性、そして今後の展望についてお聞かせください」
東井氏:「現在は中学校の英語から『教科書AIワカル』を運用してますが、2026年の春に向けて教科を少し拡充していく予定です。生成AIはベースの技術の進歩が速く、今はテキストチャットが中心ですが、画像認識や音声認識、マルチモーダル化も取り入れていきたいと考えています。今日、お見せした『教科書AIワカル』が完成形とは思っていませんので、教科を増やしていくと共に対象を増やしてき、場合によっては機能を増やしていきながら、教科書を基盤にした生成AIのサービスの可能性を広げていきたいと思っています。一緒に議論や連携できることがありましたら、お声がけいただけたら嬉しいです」
最後は石戸の「子どもたちや保護者、そして先生や学校現場が安心して活用できる生成AIがついに登場したという印象を受けました。同時に、東京書籍さんがこれから教科書のあり方をどのように進化させていくのか、その未来に大きな期待を感じるお話でした」という言葉でシンポジウムは幕を閉じた。