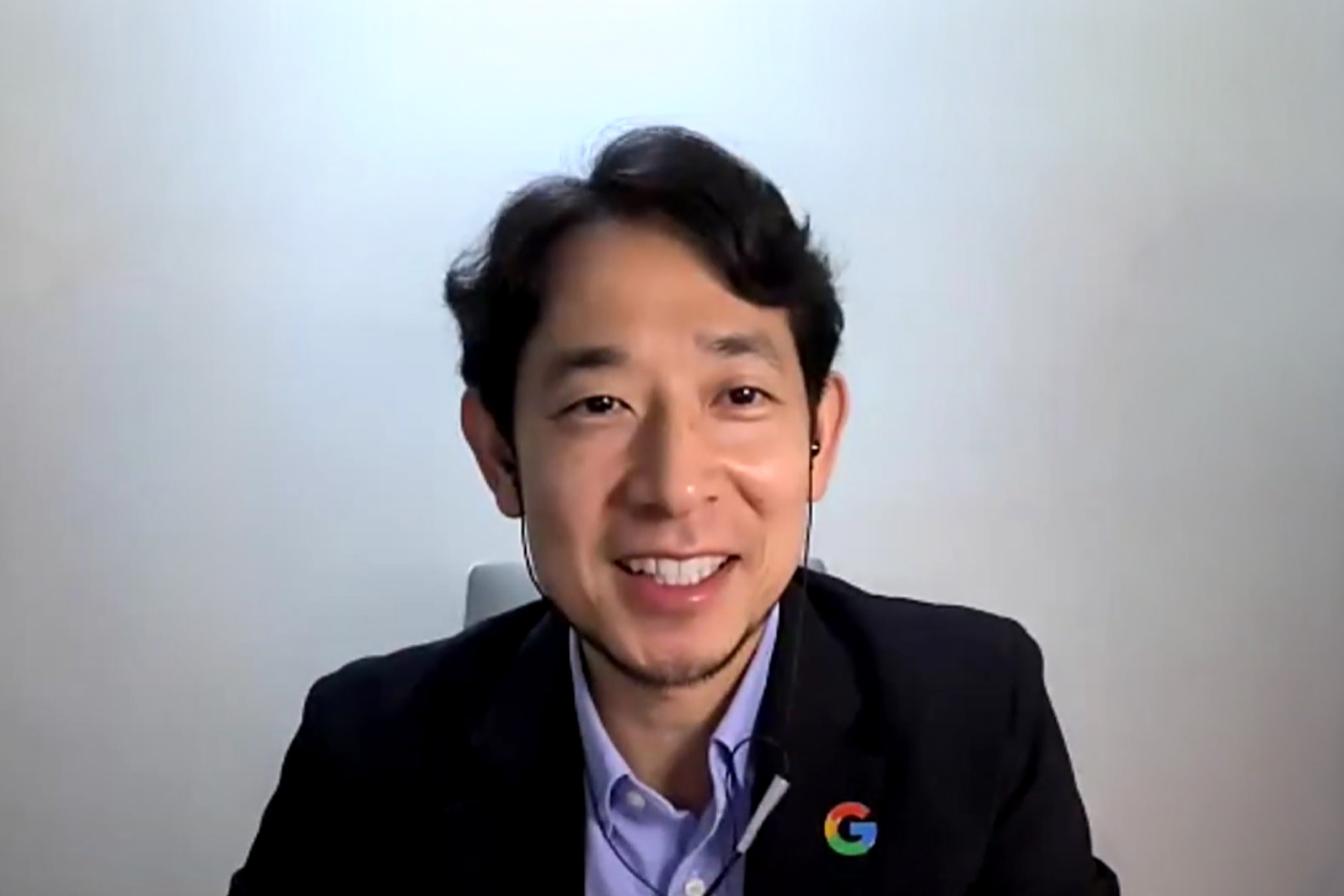概要
超教育協会は2025年5月21日、特定非営利活動法人AI教育推進機構 代表理事、武蔵野大学名誉教授、東京工科大学名誉教授、学習分析学会理事の上林 憲行氏を招いて、「AI響創人財像とAI響創型教育イノベーションについて」と題したオンラインシンポジウムを開催した。
シンポジウムの前半では、上林氏が情報科学やAIの進化に応じて求められる教育プログラムの再構築について講演し、後半は超教育協会理事長の石戸 奈々子氏をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。
>> 前半のレポートはこちら
>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画
「AI響創人財像とAI響創型教育イノベーションについて」
■日時:2025年5月21日(水) 12時~12時55分
■講演:上林 憲行氏
特定非営利活動法人AI教育推進機構 代表理事、武蔵野大学名誉教授、東京工科大学名誉教授、学習分析学会理事
■ファシリテーター:石戸 奈々子
超教育協会理事長
 ▲ 写真・ファシリテーターを務めた
▲ 写真・ファシリテーターを務めた
超教育協会理事長の石戸 奈々子
シンポジウムの後半では、超教育協会の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。
生成AI とどう付き合い、どう活用するか教育環境のグランドデザインが必要
石戸:「このシンポジウムの視聴者は、初等中等教育に関心が高い視聴者が多いため、まずその視点から質問させてください。日本は2020年度からようやく1人1台端末が整備され、プログラミング教育が必修化されました。その直後に生成AIが普及し、情報教育のカリキュラムを改めて再構築する必要性がでてきています。そのことは高等教育では盛んに言われているものの、初等中等教育から一気通貫で考えていくことが大切なのではないでしょうか。上林先生としては、初等中等教育におけるAIを含めた情報教育で、どういうことをどのタイミングで学ぶ環境を整備していくと良いとお考えでしょうか」
上林氏:「Co-Intelligenceというのは、生成AIとの付き合い方の基本的な考え方、理念の話です。道具ではなくて、共鳴連鎖するようなかたちで使っていくということです。コンピュータはメタメディアという原理的な特性を持っていて、決定論的な意味合いを大前提として構築されていましたが、現在は確率論的な計算エンジン、計算モデルですよね。その統計的・確率的な計算モデルの理解に資するようなものを再構築したほうが良いと考えています。
例えば、数学が必要だから線形代数を学びなさいとなると、ANNの理解の余計なことまでを学ばなければならず、嫌になってしまうと思います。再構築の全体像の中で、幼児教育では何をすべきか、小学校では何をどこまですべきか、中学校、高校の教育プログラムの中身はどう改訂していくかを位置づけないとなりません。ただ、問題が大きすぎて今すぐにAですBですと答えるのはなかなか難しいです。こういう問題意識を共有して、再構築に賛同される方々と一緒に取り組みたいというのが私の正直な気持ちです」
石戸:「先ほどハーバード大学もAIの先生を投入するという話がありました。日本でもそういった取り組みは始まっています。まさに生成AIが登場することによって個人家庭教師のように、個人に最適化された先生に近い存在を提供することができるようになりました。これは、インプットするという意味でもアウトプットするという意味でもそうです。そんな時代において、大学の在り方というのはどうあるべきとお考えですか。それと合わせて、そのような時代において大学に入る前の過程でどんな力を育んでおくべきですか。この2点についてご意見をお聞かせください」
上林氏:「それはキークエスチョンで、明快な回答がすぐに出せるわけではないと思います。それぞれの学問はプリンシパルを自己完結的に学んでいるものの積み重ねです。一方、世の中の知識やスキルは、ある目的やコンテキストの中で有機的にカップリングされて使えるという、つまりコンテキストと非常に密度が高いものだと思います。
大学では、知識のインプットが生成AIでもオンデマンドのコンテンツでもできてしまいます。先ほどお話がありましたが、状況学習理論では、あるタスクを達成するための副産物が知識やスキルとなります。単に知識を得るための学びというのは、大学では比重を下げた方がよいのではないかと思います。本来的に、大学の学びの特徴は、ゼミや卒業研究です。自分の問題意識から先生の薫陶を受けて結果を出していくことです。教員と学生の比率がなかなか改善されていないので、サポートできないですが、私としてはそういう考えを持っています」
石戸:「これまでは、知識を積み重ねた先に初めてプロジェクト型の学習が成立するという考え方も根強くあった中、それを逆転させる学習環境を技術によって整備することが可能ではないかという話にも読み取れるかと思います」
上林氏:「仰る通りだと思います。何を教えるかということも大事ですが、どういう学びの環境や学びのスタイルを考えるかも非常に大事だと思います。私自身が試行錯誤したのは、状況学習理論に基づく教育の方法論です。要するに、これはコミュニティ・オブ・プラクティスで、先生から知識移転を受けるという形はたぶん生成AIやオンデマンドコンテンツで代替できると思います。
しかし、それではできないこともあります。学びというのは先生からだけではなく、あるコミュニティの中で学ぶということでもあります。研究所に配属されると、先生だけでなく先輩がいます。さまざまなステークホルダーがいますが、そのひとつは生成AIです。教員も自分の活動をサポートするエージェントを持ち、学生も自分のアシスタントを持つようになると、教員と学習者とそれぞれが持っているエージェント、その4者関係が、教育学習のエコシステムだと思います。それが前提になった学びの仕組み、学びのスタイルというのを考えないとなりません。つまり、学びが大学の教室の延長上で停止しない方がよいというのが私の考えです」
石戸:「今の大学の設置基準上はキャンパスが必須ですが、そういうところからの問い直しも必要だと思います。一方、コミュニティベースで学んでいくことの重要性を実現しようと思うと、大学の形式をもたないオンラインコミュニティでも良いとも言えます。オンラインで興味がある研究テーマが同じ仲間を集めるという点では、ひとつの大学に限定しない方がよりやりやすいでしょう。そうなると、ますます大学の在り方をしっかり考えないと存在意義自体が問われるようにもなっていくと思います。いかがでしょうか」
上林氏「それについても、仰る通りだと思います。コミュニティ・オブ・プラクティスの形だと、コミュニティだけでなくて色々な外部のステークホルダーと自由に相互連携ができるコミュニティをバーチャル空間で作れます。そういうものこそ、これから意義が大きくなるし、物理的な学習環境と制約を超えて、新しくできることはあると思います。時間や空間的な制約は、ICTの進歩でクリアできました。もうひとつ、知的なアンプリファイアーとしての生成AIが手に入ったわけです。その2つを前提にした教育環境や教育スタイルというのを本当に考えていかないとなりません」
石戸:「視聴者から、これから求められる人材像に関する質問もいくつもきています。例えば『人間にしかできない価値創造とはどのようなものになるでしょうか』というものです。もうひとつは、『シン人材像にはどのような倫理観や社会的責任感が必要だと思われますか』というものです。リンクする質問かと思いますが、いかがでしょうか」
上林氏:「生成AIが2002年の11月に登場してからずっと考えていますが、なかなか簡単な結論は出せないです。生成AIと響創して自分の活動をしていくという前提は変わらないと思います。では、人間固有の能力として何を伸ばして、どうやって育んでいけばよいか、それはたぶん情報科学分野の我々だけでは荷が重い答えではないかと思っています。
ただ、生成AIが関わるのは知性です。人間には感性や身体性、倫理性、理性もあります。だから感性や身体性や倫理性、理性を、人間固有のものとしてさらに磨きをかけないとなりません。知性の部分は、響創的な関係をうまく身に付けるのがひとつの姿かなと現時点では思っています」
石戸:「人材像にどのような倫理観や社会的責任感が必要だと思われるかに関してはいかがでしょうか」
上林氏:「これも簡単に答えが出せる問いではないと思います。AIの教育については、AIに関する倫理規定をしっかり叩き込まないとならないと言われています。蛇足ですが、最近の生成AIを使っている中で感じているのは、生成AIのアウトプットが自分の想定以上のものが出るようになってしまったということです。そうすると、自分がもっと勉強しないと、生成AIのアウトプットを理解して責任を持って判断して実行することにはなりません。そこに倫理も含まれると思います。自分の想定内で生産性高くアウトプットしてくるという装置だったのが、さらに進化して変容しているので、断定的にAですBですと明言するのは難しいと思っています」
石戸:「このような質問もきています。『どうやってその答えが導かれたのかが人間の側は分からないAIの答えを、アプリオリに受け入れるデジタルネイティブの人たちが増えていくことに孕む危険性についてどのように捉えていらっしゃるか』というものです」
上林氏:「それはよく言われることですね。使い方を間違えてしまうと、人材が育たない。それを危惧しています。生成AIでも、答えの論拠と推論過程、因果関係というのを合わせて出すということが研究されています。そういう意味だと、まだ生成AIも発展途上で生煮えだと思います。出てきたアウトプットに関して、その論拠とファクトや、それの推論過程、結果を導出するための因果関係などを必要に応じてきちんと説明することは、必要になると思いますし、鋭意、研究もされています。だから間もなくそれに相当するものが手に入ると私は楽観的に考えています」
石戸:「視聴者から『何のために何を学習するのかということに関する先生の現段階でのお考えを教えていただきたい』という質問です」
上林氏:「これは、また非常に根源的で難しいクエスチョンですね。やはり、生成AIと対話することによって自分の知識、社会が広がるということだと考えています。本来的に持っている知的好奇心を豊かにする、そういうものとして生成AIと付き合っていきたいと思っています」
石戸:「小さい子がAIを使うことに関する質問をよく受けますが、小さい子の『なぜ?』や『なんで?』に親がすべて答えられるわけではない中で、なんでも答えてくれる生成AIの存在は大きいと感じます。もちろん答えが正しいか正しくないかは親子のコミュニケーションで問い続けなければなりませんが。
しかし、色々なことに多角的な視点で答えをくれる存在というのは、まさに知的好奇心を刺激してくれる存在そのものだと思いますし、小さな子から大人まで人間が知りたいという根源的な欲求に応えてくれて、満たしてくれるものが生成AIではないかと思います」
上林氏:「経験的に言いますと、大学なら大学という枠組みの中で『問いのモデル』のリアリティを上げていくことが大切で、それによって多角的な視点を提供してくれるし、批判的なフィードバックももらえます。つまり、生成AIはリアリティがあり、多角的でクリティカルなもので、求めに応じて対話して自分の成長を促すという装置と認識すべきだと思います。自分の出した課題をチートするための道具の使い方は、ミスリーディングになります。ミスリーディングになるというのは、生成AIの本質的な素性や提起している問題が何かを関係者は深く理解して構築すると思います。生成AIがすごく役に立ちそうだから、その活用ノウハウをプロンプトエンジニアリングでやるというのは、時代遅れになります。そこでやっていることは結局、早手回しで生成AIが全て取り込んでいる。そういう一過性のものと本質的なものをきちんと区分するのは今後、科学に関わる人の責任だと思います」
最後は石戸の「私たちが意識するしないに関わらず、ありとあらゆる環境にAIが組み込まれていく時代になりつつある今だからこそ、AIの利活用の格差が広がらないように、教育環境のグランドデザインが必要なタイミングだと思いました」という言葉でシンポジウムは幕を閉じた。