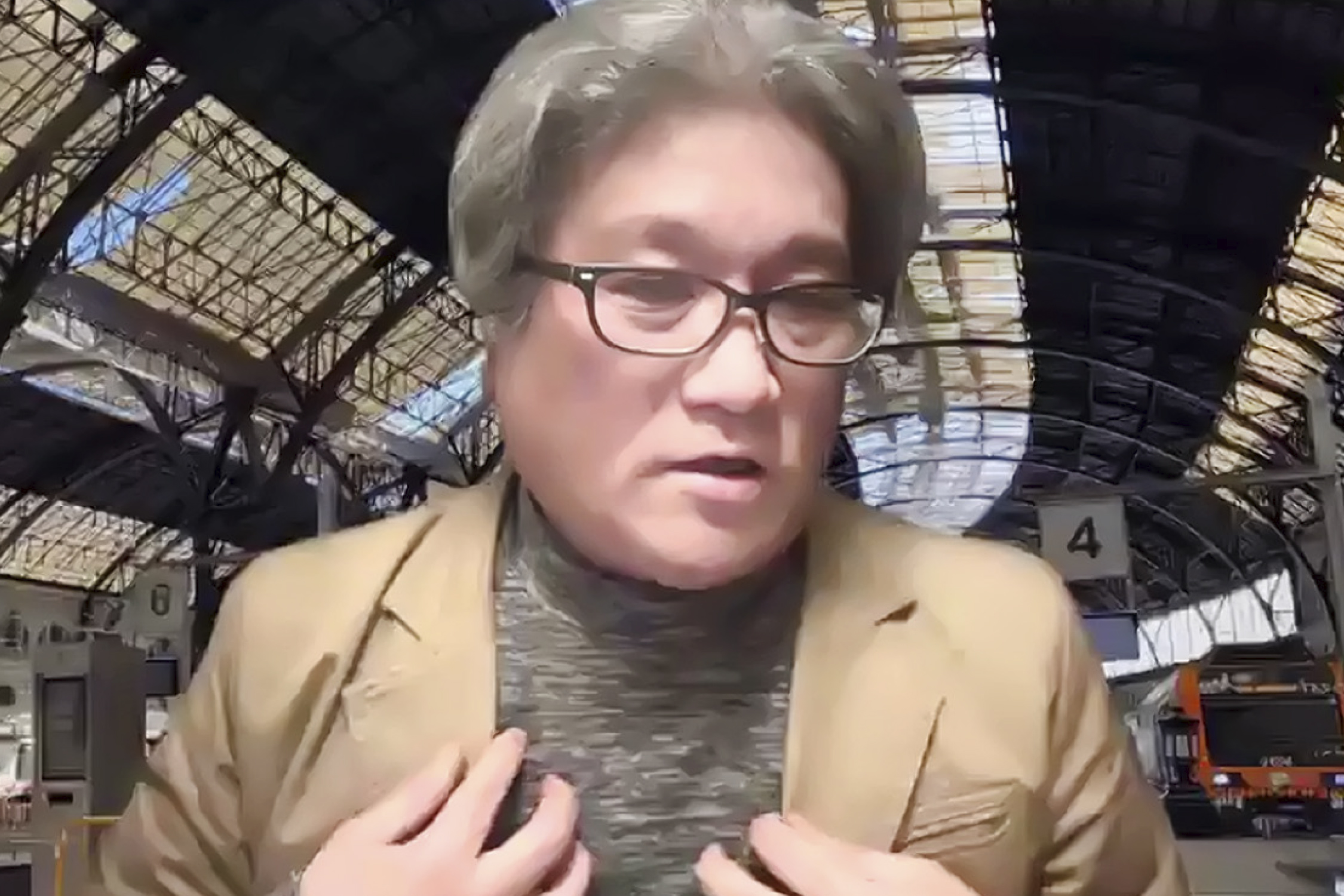概要
超教育協会は2024年12月25日、うつほの杜学園の発起人・代表理事の仙石 恭子氏を招いて、「世界遺産・熊野古道の地で探究型グローカル小学校を実現する『うつほの杜学園』」と題したオンラインシンポジウムを開催した。
シンポジウムの前半では、仙石氏が「うつほの杜学園」の設立経緯やコンセプトについて講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その後半の模様を紹介する。
>> 前半のレポートはこちら
>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画
「世界遺産・熊野古道の地で探究型グローカル小学校を実現する『うつほの杜学園』」
■日時:2024年12月25日(水) 12時~12時55分
■講演:仙石 恭子氏
うつほの杜学園 発起人・代表理事
■ファシリテーター:石戸 奈々子
超教育協会理事長

▲ 写真・ファシリテーターを務めた
超教育協会理事長の石戸 奈々子
シンポジウムの後半では、超教育協会の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。
グローカルな視点で自分軸を育む教育に視聴者の関心が集まる
石戸:「今回、学校設立にあたり、日本の教育に対する課題意識も背景にあったのではないかと思います。仙石さんから見て今の日本の教育の最大の課題、それからそれが起きてしまっている要因は何だと思いますか」
仙石氏:「大きく言われていることですが、大学入試という進学のための教育が私たちの少し前の世代からすごく強まっており、そもそもの学ぶことの意味が変わってしまっているところが1つ、大きな課題かなと思います。今は総合選抜で新たなやり方が制度としては出来上がっていますが、まだまだ先生の意識もそうですし、保護者の方々も状況を知らない中で、そういったところから脱却していくのには時間がかかると思っています」
石戸:「今、さまざまな新しい学校が生まれています。私たちのオンラインシンポジウムでも、特徴がある学校を設立されている方々にお話をうかがってきました。このようなことが同時多発的に起きているのは偶然ではないと思いますが、いかがでしょうか」
仙石氏:「私のように教育関連のバックグラウンドもなく、保護者の立場から学校を立ち上げることは今の時代だから実現すると思っています。社会が今、劇的に変わっている中でコロナ禍もあったり、生成AIが出てきたり、誰もが教育が変わらないといけないという意識がすごく強くなっています。保護者と話していてもそう感じますし、寄付を集める中で企業の方々とも話をしますが、みんながそれを感じていることが大きいと思います。教育業界の中だけでなく、そうではない人たちが教育に関わる流れが起きてきていると感じています」
石戸:「仙石さんご自身は在学中に留学されていたほか、ビジネスでも国際的にご活躍されていましたが、海外においてもその認識は同じなのでしょうか」
仙石氏:「私は世界全体を把握しているわけではなく、情報だけで知ったところもありますが、日々、ヨーロッパとつながっていますので、そこに関してお話しすると、そんなに大きく変わっていないと思います。皆さん、それなりに国ごとの課題はありますが、民間が動いて新しい学校ができるという流れには、まだヨーロッパはなっていないのかなと感じてはいます。
そこは元々、ヨーロッパには大学進学のために教育があるといった状況にはなっていません。アジアに関しては、逆に経済の発展と共に教育に対して意識が高い方々が増えていると感じています」
石戸:「実際にどう通うかに関する質問も複数届いています。『県外からの教育移住という言葉を使われていますが、その場合、基本的には家族で引っ越しをするのか、それとも寮などを考えているのか』というものです。いかがでしょうか」
仙石氏:「寮を作る計画はなく、家族で移住してきていただくことを前提で考えています。それは小学生の時期には、やはり親御さんと一緒にいるのがよいのではないかという私たちの考えからきています」
石戸:「教育移住という言葉を聞く機会が増えています。例えば軽井沢は教育移住の先としてよく聞きますが、教育移住はどのくらい増えているのでしょうか」
仙石氏:「全体的な人数までは把握はできていないのですが、軽井沢がありますし、和歌山県にも昔から『きのくに子どもの村学園』があるほか、シュタイナー学園など、日本全国でさまざまな規模の学校が増えていると思います。そういった学校の中身を聞くと、多いところで8割、9割を超える方々が移住者です。これは日本全国場所を問わず発生している現象と思っています」
石戸:「移住者を受け入れるにあたり、どのような行政との連携がありますか。学校設立においても行政とは密な関係があると思いますが、自治体は教育移住や新しい学校の設立についてどのように捉えているのか。そして、どのようなサポートがあるのかについても教えてください」
仙石氏:「まず、和歌山県田辺市にたどり着く前に5つくらい、和歌山県の中の自治体を回りました。今の教育がどのように変わってきているか、私たちの学校のコンセプトについて、また日本全国で教育移住が起こっているというデータを示してきましたが、全ての自治体の方が非常に驚かれていました。教育が変わってきていることも地方自治体ではほとんど知られていないですし、それによって移住まで起きているという現状をほぼ皆さん知らなかった状況です。田辺市では実際の説明会で、他府県の方が毎回来られて、私たちは軽井沢のような事例も説明して移住者に対するフォローも必要であることを訴えており、地域おこし協力隊の仕組みも既に作っていただいて、そこにスタッフも入って空き家を探したり、今までうまく活用できていなかった団地を貸し出す準備をしていたり、さまざまな連携を行っています。毎回説明会に他府県から実際に来られて、居住場所を探すことや教育に共感される人たちを目の当たりにして『本当に来たね』と驚かれているところがあります」
石戸:「先生になる方々に関する質問です。今回、掲げているようなグローバルな視野で英語を活用して、そして探究型の学びを提供できる先生をどのように育成するのか、もしくはどのように採用するのでしょうか」
仙石氏:「大きなテーマや探究型の授業を作ることについては、先ほど紹介した校長の市川と、私自身もIB(国際バカロレア)の教員資格を持っているほか、もう1人既に取得して、しかも他の小学校でIBの教員として働いた経験のあるスタッフが中心となり、今、探究型授業の仕組み作りとテーマ設定、探究の授業の作り方を話し合いながら進めているところです。
それ以外の教員は未経験ばかりですが、アドベンチャーワールドのように異なった業種から入っていただいたり、地元で既にローカルや自然と繋がる授業はやってきているけれども、世界の部分はまだやってきていなかったり、さまざまなバックグラウンドを持つ教員の採用を半年くらい前から進めています。まずはそういった理念を共有し合い、世界、地域、自然とつながるカリキュラムとはどういうことなのか、一緒に考えながら作り続けている現状です。
またネイティブのアメリカとロシア出身の教員も入っていますが、日々、教員同士でもそういったネイティブの人から意見も多く出るなど、教員たちが今まさに探究しています。そういった中で、非常にアクティブな授業作りが進んでいるところです」
石戸:「教科書会社の方から、『どのような教材を使用するのか、どういう教材を求めていらっしゃるのか』という質問があります。皆さんの学校のみならず、これから先、地域での特色ある探究型の学びは増えていくと思いますが、教材等に関する希望がありましたら教えてください」
仙石氏:「IB(国際バカロレア)の場合は、概念教育と言って概念で学び、フレームワークを作っていく考え方があります。これはIBだけではなく、例えば話題のミネルバ大学などでも概念を使っています。これは世界的な流れとしてあるのかと思いますが、これから大事になっていくのは教員の問い作りのところだと思います。経験がない先生方が問い作りをしやすいガイドブックのようなものがあれば教科書としても参考になるのではと思います。
地域ごとのリソースをこれから教育にどのように使っていくのかは、既に各自治体でさまざまな取り組みがされていると思いますが、バックグラウンドがまったく異なる学校でも使いやすいという視点では、抽象的概念の考え方として使っていける教材があると良いと思っています」
石戸:「生成AIの普及に伴い、問いを立てる力が今まで以上に注目を浴びていますが、IBの学びとの親和性が高いですよね。視聴者から次のような質問がきています。『どのようなお子さんに入学して欲しいですか。教員、児童、保護者に求める資質や能力はどのようなことがありますか』というものです。小さい子どもたちも来るので、その時点で求める力というより、先ほど関係力、探究力、想像力という言葉もありましたが、どういう資質、能力を育んでいきたいのか、そして教員や保護者にもどういう力を求めるのかについてはいかがでしょうか」
仙石氏:「私たちは、子どもたちに求めるところはあまりなく、入試の考え方自体も行動観察のようなことをしますが、私たちが提供する授業を楽しめるかどうかをルーブリックにして判定をすることを行っています。
ただ、入学するときに6~7歳だと、子どものそのときの素質より、入った後に伸びる方が無限大だと思っています。私たちは理念受験という言い方をしていますが、むしろ保護者の方々の子育ての考え方と私たちの理念が合致するのかどうかの相性を気にしています。
教員に関しては、『いっしょに学ぼう、創ろう、冒険しよう』というマインドがあるかどうかだと思っています。教員の中には、まだ英語は得意ではないなど、全てが完璧に揃っている者ばかりなわけではないですが、それでも英語を自分も学んでいこうという気力があるとか、また、やったことがない探究の授業も積極的に作っていきたいとか、世界と地域と自然とつながるということも、言うことは簡単ですが本当につながっていこうとするとかなり大変です。そういったところへの理解とか、スキルがあるかを教員に対して求めています」
石戸:「卒業後の進路のイメージやそれに対するサポートに関する質問もきていますが、いかがでしょうか」
仙石氏:「私たちは小・中学校の義務教育の9年間で教育を行います。この先、まず自分軸を作っていくという年代ですので、9年経った後におそらくさまざまな進路を希望する子どもたちになっています。それが目指すところだと考えています。地元の高校に入るという選択をする子もいるでしょうし、高専や農業、芸術など、既に自分で見つけて専門的な高校に行きたいという子も出るでしょう。海外に出ていきたいというお子さんや、IB(国際バカロレア)のADP校に進みたいお子さんなど、さまざまな進路が出てくるのではないかと想定しています。
その中で私たち9年間の最後の1年間をできるだけフリーにして、9年間の教育をできるだけ8年間にまとめ、最後の1年間は次に描く自分の将来に向かって準備をするほか、それを探究するような時間をできる限り確保したいと思っています。それぞれの進路に合ったサポートをしていきたいと思っています。まだ具体的な仕組み作りにまで行けていないのですが、大きな理想にはなりますが、そういった考え方をしています」
石戸:「幅広い進路を生み出すことが1つのゴールというのは素敵な表現です。一人ひとりが多様な中で、自分の好きな道を自分軸に基づいて見つけられる、それが理想的であると思います。地域とつながる、それから世界とつながると言葉で言うことはできても実はすごく大変だというお話がありました。その通りだと思います。現状において地域、それから世界とはどういうつながりがあり、どういう反応があるか、そして地域や世界に対して逆に皆さんがどういう影響を与えているかについてはいかがでしょうか」
仙石氏:「今、地域の方々とは日々交流をしていますが、まず時間軸がすごく違っていて、1回会うと2時間ぐらいこうやって会話をしながら、その中で皆さんがこの場所で育んできた、さまざまな知恵などを拝借するような時間軸で過ごしています。地元の方々に関しては、今まで育んできた歴史、文化、知恵とか、そういったものを持ってはいますが、それを教育につなげていく思いをされていない方ばかりですので、ワークショップなどにもそういった地元の方々にも入っていただいています。子どもに対する接し方を私たちが少し説明しながら、それも地元の方々に楽しんでいただいている、本当に新しい教育に触れられているところがあります。
世界とのつながりについては、この学校はまだ開校もしていなくて校舎もまだ工事中ですが、韓国からソウル大学の教授が視察に来られたり、ミネルバ大学の教授が来られたり、ネパールの学校とつながりがある方が来られたり、デザインフォーチェンジという世界の子どもたちがプレゼンをする大きなプロジェクトの日本代表の方が来られたりという感じです。このように、世界中の教育関係者に興味を持ってこの場に来ていただき、既に交流が始まっています。それも、この場所柄ということももちろんありますし、世界と地域と自然とつながってやっていくというコンセプトが、そういった方々にも響くということは体感として思っています」
石戸:「インクルーシブ教育に関しても複数人から質問がきています。『学校デザインが学びの多様化校のあるべき姿として具現されているように感じました。インクルーシブ教育についてどのようにお考えですか』というものや、『発達障害やグレーゾーンと言われているお子さんの受け入れについてはどのようにお考えですか』というものもきていますが、いかがでしょうか」
仙石氏:「私たちの基本的な考え方として1クラスに1人の先生というところまでは決まっていますが、その中で授業が受けられるお子さんであれば受け入れていくという考え方をしています。ただ、その1人が付きっきりで、もう1人サポートが入るところまではできませんので、そこまでが必要かどうかというところは見極めなくてはならないと思います。私たちの教育を楽しめるかどうかの素質があると判断したお子さんは受け入れる予定です。ここについては、保護者の方々の理解に時間がかかり、対話が必要になるかなと思っています」
石戸:「独自の教育をしつつ、卒業証明を得られるのはとても大事なことです。特別な学びは、現在の教育へのアンチテーゼとなる発想から起こりがちな中で、公的な基準を満たすのは大変なことだったと思います。設立しようとしたコンセプトに、『日本で規定されている教育に則ったことをするにあたっての思いや苦労を聞きたい』という質問もきています。私も同感でして、さまざまな苦労があったと思います。一条校として設立することに対する思いや、実現に当たっての苦労を教えてください」
仙石氏:「フリースクールのような形で学校法人にせず設立する方法もありましたが、学校法人にこだわった理由というのは、やはりこの1つの学校という点を打つことで、少しでも学校教育や他の教育にも何かしら貢献していきたいという思いがあったからです。学校の学習指導要領との辻褄合わせは確かに大変で、教員の方々が非常にそこに苦労している部分ではあります。
ただその一方で、学習指導要領はかなり多様にできるように変わってきており、教員側の捉え方や学校の捉え方次第でかなり実は自由にできるものではあります。教育業界に属していない方はあまり知らないと思いますが、自由度があるのは事実です。そういった中で、私たちはIB(国際バカロレア)のルールにも則る必要があります。がんじがらめにもなり、普通の授業作りよりはかなり手間がかかり、しかも手作りとなりますが、なんとかやっているところではあります。
一条校にしていくには、自治体との連携がどうしても必須になってきます。ここに関しては和歌山県や田辺市との連携がどうしても必須で、ここが苦労した部分です。教育に関心がない方や今の教育に特に疑問も持っていない議員の方、さまざまな役場の方もいらっしゃるので、そういった方々との対話に非常に苦労しました」
石戸:「視聴者からは『国内外で参考にした学校や教育の事例があれば知りたい』という質問も届いています。IBを基準にされていると思いますが、学校の作り方や仕組み、空間、地域との連携の仕方など、参考にした事例がありましたら教えてください」
仙石氏:「日本でオルタナティブと言われているところはさまざま見てきていまして、『きのくに子どもの村学園』にも、シュタイナー学園にも行きました。いろいろな部分で参考にしているところがあります。かなり影響を受けたところで言いますと、東京都中野区にある『東京コミュニティスクール』です。実は2学期の数カ月間、週に1回入らせていただいて、かなりじっくりと学校を見学させていただきました。学校を設立された久保 一之氏や、さまざまな先生たちにも密に対応していただきまして、『東京コミュニティスクール』の教育には強く影響を受け、参考にさせていただいている部分があります。
また、プロジェクトを立ち上げたのが2020年であり海外にほとんど行ける状態ではない中だったので、まだ海外校を見に行くことができていません。学校の中身というより、あり方で参考にしたのはインドネシア・バリ島の『グリーンスクール』です。この学校は学校環境で参考にしています。またサマースクールなど、短期でも学べる仕組みがあるところは非常に参考にしています。あと学校ではないのですが、イタリアから影響を受けている部分も多くあります。学校とは自分自身が将来、仕事をするために学ぶこともありますが、ウェルビーイングに幸せに生きるための経験やスキルを得ることや、ペアレンティングのような親になる準備が残念ながらできていない状況にある中で、いずれ親になっていくとか、本当に幸せに人間として生きていくために、どういった学びをしていくのかといった視点では、イタリアやヨーロッパの方々の生き方、空間作り、日々の楽しみ方、そして教育の中のあり方はすごく参考にしています」
石戸:「うつほの杜学園にたくさん子どもたちが集まってくることを願ってやみませんが、一方で全国の子どもたちのことを考えると、うつほの杜学園のような学びの場がたくさん生まれるといいなという気持ちもあります。他の地域での横展開の可能性についてお伺いしたいです。また、最後に日本の教育の未来に対してコメントをお願いします」
仙石氏:「横展開については、まだそこまでは正直考えられていません。ただ私たちの取り組みを見て、それぞれの地域で同じような取り組みが立ち上がり、そこで私たちが何か相談に乗るといったことになると非常に良いと思います。自分たちの町のことは自分たちでやるという、そこのところがすごく大事だと思っていて、私が全国に作りに行くとよりは、それぞれの地域の人のそれぞれの地域への想いから、自分たちの子どもたちを自分たちで育てていくという、そういったカルチャーを大事にしていきたと思います。
教育に対して課題は本当に多いと思いますが、私のように教育業界ではない人たちが参画していくムーブメントが起きていると強く感じています。私は非常に日本の教育の未来に関してはポジティブに捉えている部分が大きいです。みんなの教育をみんなで作っていく気持ちで、そういったスピリットを広げていきたいと思います」
最後は石戸の「2024年のラストを飾るのに相応しい非常に明るい未来を感じるお話でした」という言葉で、シンポジウムは幕を閉じた。